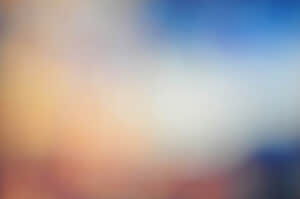「みんなもっと迷惑を掛け合って生きたらいいと思うんです」
気仙沼にあるゲストハウス「SLOW HOUSE @kesennuma」のオーナー・杉浦恵一さんは、そう言った。
東日本大震災の後、地元である愛知県から宮城県気仙沼市に移住し、2011年11月11日、東日本大震災の被災者への祈りを込めてキャンドルを灯す「ともしびプロジェクト」を立ち上げた杉浦さん。その後、やりたいことをカタチに出来る大人の秘密基地のようなシェアオフィス「co-ba KESENNUMA」や、”余白”をテーマにしたゲストハウス「SLOW HOUSE @kesennuma」など、気仙沼の地で人と人がつながる場をつくってきた。
そんな杉浦さんの口から出てきた「迷惑を掛け合って生きる」という言葉。そこに込められた想いを探るべく、幼少期から今に至るまでの杉浦さんの「面白い」人生に迫った。

1986年熊本生まれ、愛知出身。38歳。ヒッチハイクで旅をしながら暮らす方法を模索するさなか、東日本大震災が発生。東北へ支援に向かう。2011年夏、宮城に拠点を移し現在は気仙沼市に移住。同年11月、SNS上でキャンドルナイトを行うことで、全国からの思いを繋ぐ「ともしびプロジェクト」を立ち上げ、その後キャンドル工房を設立。気仙沼初のシェアオフィス「co-ba KESENNUMA」や、企画、デザイン、動画などのクリエイティブ製作チーム「イマジンスタジオ」、余白をテーマにしたゲストハウス「SLOW HOUSE @kesennuma」、人と空き家をつなぐ「さかさま不動産気仙沼支局」などを立ち上げ、現在は2法人の代表であり4児の父として活動中。
人生の最初の転機は、大事故を機に出たヒッチハイク旅
「もともと僕は、『遊びをアップグレード』するのが好きで。自分だけでなく、みんなが楽しめるように、学年関係なくドッジボールをしたり、自分で考えた新しいルールを追加したりしてよく遊んでいました」
そう話し始めた杉浦さん。話が幼少期にまで遡ったのは、杉浦さんの「遊びをアップグレードする癖」が、その後の人生を大きく動かすことになったからだ。
「中学に入り、ドラムを始めてバンドを組み、ライブハウスに出入りし始め、“悪い先輩たち”とつるむようになりました。その頃から、学校の校舎に向かってストラックアウトをやったり、夜の工場で鬼ごっこをしたりと、『自分たちだけが楽しい』遊び方をするようになったんです。バンドが解散してからは、いたずらに拍車がかかり、高校3年の進路選択の時期には、2回停学処分になりました。
反発するようになった背景には、卒業したら杉浦恵一としてではなく、肩書きのある『何者か』として社会に出ることを求められたことが大きかった気がします。進路なんてわからない。何者かになる前に、一個人として社会に出て色々な世界を見たいという想いがありました」
そんな杉浦さんの人生が大きく動いたのは、高校3年の冬頃だった。
「停学中のある日、車を運転して友人の家に行った帰り、赤信号を無視した車に衝突されました。フロントガラスを斜めに飛び出して7メートルほど吹っ飛ぶ大事故に遭ったんです。気づいたら病院のベッドの上で手術が終わったあと。事故前後の記憶はありませんでした」
なんとか一命をとりとめ、その後高校を卒業した杉浦さん。進路選択のときに感じていた「何者でもない自分として社会に出たい」という想いが、事故という思わぬ形で現実になった。半年後の再手術まではしばらく自宅療養。だが、やんちゃだった杉浦さんが半年間家でじっとできるわけもなく、事故から数か月経ったある日、3000円を握りしめて家を出た。行き先は、東京。ヒッチハイクの旅をすることにしたのだった。

「愛知の田舎に住んでいたこともあり、一度は自分の意思と足で東京に行ってみたいと思っていました。ヒッチハイクで2日で到着。東京には、もともとバンド時代の友達がいましたが、他にも全然知らない人たちにも泊めてもらって良くしてもらいました。そのときに出会った人たちの話が面白くて面白くて。『なんて狭い世界で生きていたんだ!』と思いましたね。
それから各地を旅したり、アルバイトをしたりして過ごしていました。知り合いが誰もいない沖縄では、財布を取られ、免許もお金も無くなり、ケータイも故障。『自分はこの状況をどうできるんだろうか?』と考えながらも、そんな状況さえ『面白い!』と思ったんですよね(笑)そのあと、22歳で四国のお遍路を歩き、24歳のときに無一文で旅に出ました」
ボランティアをきっかけに訪れた気仙沼で始めた「灯す」という活動
そのまま旅を続け、半年間かけて、愛知から太平洋側を通って北海道、日本海側を経由して愛知に戻ってきた杉浦さん。次に訪れた転機は、2011年。旅から一時的に実家の愛知に戻っていたときに起こった東日本大震災だった。発災から一週間経たずして、杉浦さんはすぐに東北へと向かった。
「無一文で旅をしていた時に東北も周っていて。お世話になったし、自分にできることがあるなら……と思って向かいました。福島で炊き出しや物資の運搬などをしたあと、縁があって気仙沼に。そこでは、被災したワインバーをボランティアのための拠点にする活動をしていました。被災した人たちが、この状況のなかで、どう立ち上がり、何が生まれていくのか──そこにいる一人ひとりの人間ドラマを日々目の当たりにしていた気がします」

そうした経験や、他のボランティア、現地の人たちとの出会いは、二度と訪れないし、このタイミングじゃないとできないこと。そう思った杉浦さんは、気仙沼にとどまることにした。
それから数か月たった2011年11月11日、杉浦さんは仲間たちとともに「ともしびプロジェクト」を立ち上げた。毎月11日に、全国、全世界の人たちにキャンドルを灯してもらい、その写真と想いをSNSに投稿してもらうという企画。プロジェクト始まりのきっかけは、杉浦さんがボランティアをしていたとき、何人かから言われた「忘れないでほしい」という一言だった。
「あるとき、キャンドルのイベントに参加して、それがすごく良かったんです。火が灯る姿が綺麗なだけじゃなくて、心が動かされる体験で。当時、県外に住む知り合いのなかには、『何か東北の人たちのためにしたいけれど、どうやって支援したらいいかわからない』という人が多かったのですが、そのイベントに参加してみて、離れていてもキャンドルの灯りを灯すことで想いを形にできるかもしれない、と思ったんです。『灯す』ことを通してつながりを生み続けられるし、色々な人が投稿することで、『忘れられていない』ことが表現される場になればいいと思いました」
宗教、宗派を越えて。想いをひとつにつながっていく
千年に一度の大震災から生まれた希望の明かりを、千年先まで灯し続けていく──そうした想いで今日まで続けてきたともしびプロジェクト。杉浦さんは、震災のことや震災の時代を生きた人の想いを、形ある「モノ」ではなく、灯すという「活動」として、後世に残し続けたかったと言う。

「時代によって、『正義』って一気に変わるじゃないですか。たとえば、百年前は人を殺して英雄になった人もいるけれど、今は違いますよね。それくらい大きくひっくり返ることがあります。だから、『これ』という一つのメッセージを伝えることも必要だと思うけれど、その時代時代で、参加した人が考えさせられたり、時代を超えて受け取れるものがあったり、活動として『みんながやり続けないと残らない』ものをつくるのが良いんじゃないかと思ったんです」

ともしびプロジェクトの発足から7年目の2017年、杉浦さんは、「すべての命」を軸に人々が集う場「命灯会」を発足。今は亡き「命」に想いを馳せることは同時に、今生かされている私たちという「命」を感じなおしたり、考えなおしたりすることでもある。そんな想いのもとつくられた命灯会は、宗教や宗派を超えて人々が集まり、気仙沼以外でも国内外合わせて30か所以上で開催されてきた。
「活動を千年間続けることを決めたとき、千年前にどんなことがあったか、今に何を伝えているんだろうって遡ってみたんです。それで辿り着いたのが、宗教でした。そんなタイミングで、津波に流されて生き残ったお坊さんと出会い、仏教の面白さに気づいたんです。そのお坊さんにも加わってもらい、一緒に活動を始めました。

また、長く続く活動を目指していたので、宗教自体にも興味を持って。それで、色々な宗教の人と会ったとき、みんなで『灯す』ことで、宗教や宗派という枠を越えて表現できるんじゃないかなと思ったんです。共通する一つの目的のもと、一緒に何かをすることで、さまざまな壁を取っ払える。そんな可能性を感じた瞬間でした」
「迷惑を掛け合う関係性」が生きやすさにつながる
「灯す」という活動を通して、人と人、そして想いをつなげてきた杉浦さん。現在運営しているゲストハウスやシェアオフィスでも、これまで多くの「つながり」を生み出してきた。大学を辞めたいけれど社会の目を気にして迷っている人、会社をクビになった人、休学中でこれからどうしようか悩んでいる人など、人生の節目のタイミングにいる人たちが、多様な生き方をしている人と出会うことで変わっていく姿を目の当たりにしてきた。
そんな杉浦さんが、かつての旅や気仙沼での出会いを通して感じていること、今、世の中に問いかけたいことがあるという。
「今は昔と比べて便利なことが増え、モノが溢れています。日本は物質的に豊かになったし、サービスのレベルも高い。SNSではいつでも誰とでも“つながれる”ようになりました。だけど、リアルな人との関係性は希薄になったように感じるし、お金をもらったらそれと同等、もしくはそれ以上のサービスを提供しないといけない窮屈さがある気がします。経済中心の時代が進み、人々があまりにお金というものに価値を置きすぎるがあまり、大切なものが徐々に失われ、『なんか違う感』を抱える人が増えているように感じるんです。
お金は、私たちの多くが信用している共通概念であり、関係性を生み出すものです。お金があれば何でも手に入ると思っている人もいます。一方で、お金がなくても、信用されて関係性を築くことができれば、生きていけるのではないだろうか。生きていくために、お金に代わる何か新しい概念がきっとある──そんな仮説とともに、無一文の旅に出ました。

その旅の結果、気づいたのが、『お金がない方が面白い』ということ。世の中には、『誰かを助けたい』という想いが溢れていて、お金がすべてではないことを体感しました。旅中は、お金がないから誰かの世話になり続けなければならないし、それは誰かに迷惑をかけることでもあります。世話をする側は、金銭的にも時間的にも負担が増える。ただ、お金がないからこそ生まれる偶発的な出会いがあって、それこそが人生を面白くしてくれると感じました」
恩を送ってもらったら、今度は自分も誰かに恩を送る。それがどんどんと広がっていく──そんな世界観が良いと話す杉浦さんは、気仙沼に移住後、自身の自宅で多くの居候たちを受け入れてきた。
「僕の家には、多いときは同時に10人くらい居候がいました。人が増えると食費もかかるし、色々なタイプの人がいるし、正直大変。でも、『じゃあどうすれば、お互いが一緒に面白がりながら暮らせるか』をすり合わせて考えていくことが面白いし、大切なことだと感じています。うちには子どもが4人いて世話だけでも大変なので、居候たちには家事などを手伝ってもらっていました。お互いにとって良い時間になればいいし、そういう恩送りし合える関係性こそが、生きやすい世界につながると思うんです」

自らがかつて、旅のなかで受け取ったたくさんの恩を、今気仙沼にやってくる多くの人たちに送り続けている杉浦さん。でもそれは、ただの「恩送り」ではない。裏には、杉浦さんが貫き通したい「面白がる」という生き方があった。
「大変なことを避け続けながら生きるのも良いと思いますが、大変なことにこそ、本当の面白さがあるということを私は知ってしまいました。知ってしまった以上、もう元には戻れないんです。それに出会えたこと自体、本当に幸せなことだなと思います。私はコスパ良く生きたいわけじゃない。自分のテーマにまっすぐ、せっかく生かされているのだから面白がりながら生きて死んでいきたい。
そんななかで、偶然出会わされている色々な人や物や出来事と一緒に、『面白がりながら生きる』を一緒にやっていきたい。余白をもって遊びに来て、気に入ったら居候してもらって良いんです。ぜひ一度、気仙沼に来てみてください」
ー
初めて会った瞬間から、杉浦さんからの周りには、「人生を前向きに楽しむ空気」のようなものが流れていた。その空気はまた、杉浦さんが取材中に何度も口にしていた「どっちでもいいよね」という言葉からも感じられた。どちらを選んでも、どんな状況であっても、自分の捉え方次第で楽しめるし、人生を良い方向へと変えていける──そんな確信のようなものが、その言葉の背後にあるような気がした。
「迷惑を掛けてもいい。人生を面白がって生きていく」
杉浦さんの姿が、あなたの人生をもっと豊かにするための、ほんの少しのスパイスになれば嬉しい。
【関連記事】“焦ることはないで” 余白を持って生きる大切さを伝える気仙沼の宿「SLOW HOUSE@kesennuma」
伊藤智子
最新記事 by 伊藤智子 (全て見る)
- ごちゃまぜでみんな一緒に楽しむ。ミラーボール輝く能登の古民家宿「土とDISCO」 - 2025年2月27日
- 本当の学びは教室の外に。ボルネオへの旅が教える「いのちのつなぎ方」【現地ツアーレポ後編】 - 2024年11月21日
- 美しいものを見つけ、自分の言葉にする。福岡伸一先生が、ボルネオ島で伝えたかったこと【現地ツアーレポ中編】 - 2024年11月20日
- ボルネオの生き物たちに流れる「いのちのものがたり」に触れて【現地ツアーレポ前編】 - 2024年11月19日
- 人生を面白がって生きていく。 無一文の旅が教えてくれた「迷惑を掛け合う生き方」 - 2024年8月14日