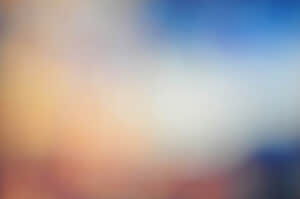「朝ごはんほど大切なものはない。良い朝は良い一日だから」
あるゲストハウスの小さなキッチンでエスプレッソを一杯、バゲットに生ハムとチーズを頬張りながら彼は言った。静かなのに独りではない空気を持つ人だと思ったのをよく覚えている。
そんな彼を横目に冷蔵庫を開ける。しまった、朝ごはんを買い忘れていた。仕方ない、と支度をして重い扉を開ける。夏本番の7月だったが、冷たく乾いた空気が入り込んできた。
この日、私はブルガリアの第二の都市プロブディフにいた。自然のすき間に人が暮らしていると言いたくなるような小さな町で、人々もなんだか素朴で温かい。その魅力に惹かれ、気づくと住み着き始めていたのだった。
プロブディフは新市街のとなりに旧市街が広がっていて、ローマとオスマン、そして少し東欧の雰囲気も相まった街だ。どこを見ても絵になるとはこのことか、とひとりごとを言いながらカメラのレンズを覗く。

ある食堂が目に入る。カウンター席で美味しそうにご飯を頬張るお姉さんを見てしまったら、入らないわけにはいかないでしょう。
中に入ると、5席ほどのカウンターが並んでいるだけの小さなお店だった。
とりあえず他の人が頼んでるものを凝視しながら、いろいろと質問してみる。見たことのないお家ご飯が並べられたショーケース。少し給食をリマインドさせられるかのような品揃えだ。

いただいたのは、ラム肉のほっこりポタージュ。私の暮らしに欠けてたシンプルだけどおいしいごはんだった。

・
別の日、止まっているゲストハウスで目にした写真の場所へ向かうことにした。「スモリャン」という名前の山に囲まれた小さな村であるということしか知らなかったが、そのポストカードを見た時、なぜか「ここに、行こう」と頭のシグナルが脳みそを駆け回るよりも先に決心していた。
2時間ほどの山道ジャーニーでスモリャンへ。村というのがちょうどいいサイズ感。

ふと町の境目あたりにあるアルメニアンチャーチの前で立ち止まると、突然「中見ていく?」とお誘いいただいた。聞いてみると、どうやら偶然にもその人は教会を管理している人だったらしく、ブルガリアの歴史を教えてもらうことができた。
1300年代の、古いブルガリア文字とギリシャ文字で描かれたイコン(宗教画)が飾られていた正教会派の教会。案内してくれたイヴァン曰く、キリル文字というロシア語圏で使われているアルファベットはビザンツ帝国時代にブルガリア人が改良して作ったものだそう。この話をしている時、彼がこの事実を誇らしく思っているのが伝わってきた。
私は本などを通して知り自分のなかに蓄積されている「知識」を、実体験を通して「答えあわせ」するようなこのプロセスが好きだ。知識や言葉が意味を持つ、その瞬間が愛おしい。
さてそろそろ帰ろうかとバス停に向かったら…「今日はもうさっきのが最後、明日の朝7時半が次のバス」とバス停のおばちゃん。仕方なく、旅にトラブルはつきもの、旅にトラブルはつきものと自分に言い聞かせながら、民族博物館のようなお店で夜ごはんを食べて、スモリャン唯一のメインロードを町の端へ向かって歩き出す。

というのも、先ほど見かけたディスコが開いてないかとかすかな希望を持っていたのだ。街灯はこの道しかついておらず、ちらほらと家の灯りが見えるだけで、人っ子一人いない。山の夜は夏でも冷える。ウィンドブレーカーとスカーフをぐるぐる巻きにしたが、寒くて足取りはどんどん速くなる。
遠くのほうから聞き馴染みのない音楽が聞こえきて、音の出元であるお店からからおじさんが出てきた。
「どうした?寒いだろう、なにか飲むか?中に入りな」
凍えてたから紅茶がほしいと注文する。ディスコでホットドリンクがかなり予想外だったようで、バーのお兄さん達と招き入れてくれたおじさんも一緒に「え?ソーサーどこにあるっけ?カップこれ?」とてんやわんや。
入ったのは近所の人々が集まって踊るような小さなディスコだった。彼らはブルガリアの蒸留酒、ルキアでおもてなしをしてくれた。ルキアは、ワインと同じくぶどうから作られており、味はヴォッカ、ウイスキーに近い。ブルガリア人の感覚ではビールは水、お酒はルキアらしく、野菜とチーズのサラダなどと一緒に夜通し飲むのだそう。
ディスコにいたうちの一人、英語が話せるタソは、首都ソフィアで働くスモリャンが地元のブルガリア愛が強い人で、スモリャンやブルガリアの土地の変化について教えてくれた。
私:「スモリャンはメインストリートしか街灯が付かないのね。思ったより静かだった」
タソ:「40年ほど前まではブルガリア人の6〜7割が村暮らしだった。子孫に繋いでいくための大きな家を建てて暮らしていた。スモリャンの外れには今でもその名残があるよ」
私:「なんで変わってしまったの?」
タソ:「社会の変化もあるね。少し前までは共産主義の時代さ。僕たちの世代から1つ2つ上の世代は今とはかなり違ったんだ。例えば、僕の知り合いは、同級生にレスリングの世界大会チャンピオンがいて、今だとオリンピックとかの大会でメダルを取ると『おめでとう』って国や教会から賞金がもらる。だけど、共産主義の時代には誰かひとりが富を持つことができなかったから、彼はずっと団地みたいなところに家族と住んでいたんだ。唯一優遇されていたと彼が話していたのは、外車を手に入れるルートを得られたこと(当時、車といえばロシア製で、新車は1〜2年待たないといけないくらい簡単に持てるものではなかった)一般の人たちは中古車を改装しながら使っていたからね」
私:「その時代のことは聞いてはいけないのかと思ってた。昔話をありがとう。ちょっとイメージが湧いたよ」
タソ:「よかった。あと、変化の理由は仕事がないからだよ。ブルガリア全体の経済が下がってきてしまっているから、田舎はもっと難しい。だから、今は地方に行くと、昔の大きなお家を保てなくて、空き家が増えて、マンションに移動している」
私:「家族が減っているってこと?」
タソ:「そうだね、若い人が減っている。自分が小中学校の時は30人学級が5クラスほどあったけど、今や10人前後のクラスが2つだ。だからこそ町の人はローカルのお店で買い物するようにしているよ。村の中で経済を回すためにね。牛乳は近くの村からフレッシュなものが届くし、それでヨーグルトだって作れる」
もちろん時の経過とともに変化するものはあるけれど、その昔ブルガリアの山間部で、山から木を切り出して大きな家をつくって、伝統衣装を身に纏い暮らしていた、素朴で美しい生活のかけらは今でもここに残っていた。
・
翌朝、タソたちは私を朝ごはんに連れていってくれた。マンションが集まるエリアの小さなパン屋さん。「これとこれがおすすめだから、帰りに食べるんだよ」と持たせてくれた。

変わっていく風景の中の、変わらない生活をこの村で垣間見た気がして、「あ、良い朝だ」そう思った。
「朝ごはんほど大切なものはない。良い朝は良い一日だから」この村に来る前、ゲストハウスで聞いたこの一言を思い出しながら、自分の中の物語の一章が完結したような、清々しい気持ちになった。
この朝にもらった優しさを他のひとに繋げて、繋げて、恩送りをしていこう。また次の「良い朝」のために。

【関連記事】自分に時間を還す旅を、地中海に浮かぶ小さな島キプロスで
【関連記事】他人をおかえりと迎え入れ、持つものを分け与える「砂漠の民のおもてなし」
juna
最新記事 by juna (全て見る)
- ブルガリアの朝ごはんが紡いだ物語 - 2024年4月23日
- ギリシャの小さな港町でファームステイをしてみたら - 2024年2月9日
- 他人をおかえりと迎え入れ、持つものを分け与える「砂漠の民のおもてなし」 - 2024年1月23日
- 自分に時間を還す旅を、地中海に浮かぶ小さな島キプロスで - 2024年1月11日