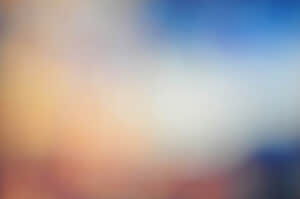気候危機、戦争、差別、分断。どうしたって暗い気持ちが一部混じってきてしまう問題だらけの今、行き場のない思いや感情を日々抱えながら過ごしている人も少なくないのではないだろうか。
かく言う筆者もそのうちの一人だ。この現実のなかで朗らかに生きるのは正直難しいときも多く、全てに目を瞑りたくなるときもある。それでも、「今を見つめたい、見つめなくては」筆者にそう度々思わせてくれるのが今回のインタビュイーのeriさんだ。eriさんは古着やアパレルを扱うDEPT Companyの代表であり、環境アクティビストとしても活動している。
=
○プロフィール:eri|えり
アパレル会社経営・プロダクトのデザイン・古着のバイイング/販売を通して、繊維産業、地球の環境課題、気候危機に対してどうアプローチできるかを模索中。またアクティビストとしてあらゆる社会問題に関心を寄せ、またそれをどう市民が課題解決のためにアクションできるのかを考えシェアし、さまざまなプロジェクトを立ち上げ運営に携わっている。
Instagram / @e_r_i_e_r_i
Image via eri
そんなeriさんの発信に触れるなかで、暮らしのなかに「旅」が多く存在していることに気づいた。「eriさんはなぜ旅をするのか」「旅を通して何を見つめようとしているのか」気になって、気づくと取材を申し込んでいた。
“あり方” を見直すチェンマイの旅
これまでも様々な国に旅をしてきたeriさんだが、しばらくの間、コロナの影響と気候変動への危機感から、長距離フライトを伴う旅から離れていた。そして2024年2月、久しぶりの旅先として選んだのは、タイのチェンマイだった。
Image via eri
「気候変動のアクティビストとして活動しながら、同時にものづくりをしているのですが、人間が身の回りにある資源でうまく暮らしていた時代とか、その頃にどういう風に何を作っていたのかといったことにすごく興味があります。『次の景色ってどんなだろうな』と思った時に、自分は『過去を学びたいな』という気持ちがすごく強い。そうした考えも、チェンマイを旅先に選んだ理由の一つとしてありました」
現地では、タイの手仕事や天然素材を使った日用品などをセレクトし販売する活動をしている友人のアトリエを訪れたり、タイの山岳民族で、身近にある素材や受け継がれてきた手法でものをつくりながら生きる、カレン族の暮らしを体験したりした。
「今は、身の回りにある資源だけで生きていくのは難しい社会構成になっているとは思うんですけど、それでも『無理がないものを使いたい』と思っていて。例えばプラスチックやポリプロピレンのケースがいくら便利だとはいえ、様々な弊害があるなかで、『本当にそれでいいのかな?』『それって本当にかっこいいの?』と思うんです。友人が扱っている水草の小物入れなどを使っているんですが、見た目もかわいいし、じゃぶじゃぶ洗えて便利だし、仮にいずれ朽ち果てても自然に還るだけで誰も傷つけないし。そういうもののほうが“いいな”と」
友人のアトリエ/Image via eri
「カレン族の村の私が訪れた場所には、昔ながらの糸紡ぎや、腰機織り、染色など、古くから受け継がれているものがまだまだ残っていて、そこでみんなが作業をしていました。その作業場の真ん中に大きな瓶(かめ)があるんです。そこにはお水が入っていて、みんな喉が渇いたら、瓶から柄杓ですくってお水飲んでいました。
それで比べてみたんですよね。オフィスでウォーターサーバーから水を飲む姿と、瓶から柄杓で水を飲む姿と。自分が『綺麗だな』と思うのは瓶のほうだなと。私もウォーターサーバーでお水を飲みますし、衛生的で便利など、そちらの良さもあるとは思うけれど、『ウォーターサーバーが当たり前になっている自分の生き方ってなんかちょっと嫌だな』と思ったんです。
料理も石臼で叩いてつぶして作っていて、機械のブレンダーを使うより、そのほうが『かわいいし美味しそう』と思ったりしました」

カレン族の村にて/Image via eri
「自分たちが普通に生きている世界のどこまでが許容範囲で、どこからがいき過ぎているのかという線引きを、自分の中でもう少しクリアにしたいというのがあるんです。『自分達が当たり前だと思っているこの世界って、本当に綺麗なのかな』とか。そっくり昔の生活をしたらいいというわけではないんだけど、便利なものとか、本当の意味で美しいもの、わたしたちの“あり方”を、ちゃんと見直さなきゃいけないなと思っていています」
ちゃんと知り、考え、伝えるために旅が必要
eriさんが代表を務めるDEPT Companyでは、ビンテージ古着を扱うと共に、アパレルを中心にリサイクルマテリアルやサステナブルな素材を用いたオリジナルのアイテムも取り扱っている。
廃棄されたビニール傘から生まれたDEPTとPLASTICITYのコラボレーションバッグ/Image via eri
現在は多くの製品を基本的に受注生産で製造しており、企画・生産時には使用予定の素材の製造工場や生産工場などにeriさんが直接足を運び、生産背景や環境などを自分の目で見に行くことを大事にしている。実際に現場を見るところから、アイデアが生まれることもあるという。
そうした工場見学の一つとして、ここ最近訪れたなかで印象に残っている話を教えてくれた。
「最近すごく学びがあったのは、リサイクルウールのジャケットとパンツを作ることになり、愛知の一宮にある工場を訪れた時の話です。リサイクルウールの素材を用意するまでには、色々な種類のものが混じった古着の山のなかからウール80%以上のニットを選別して、倉庫に運んでネームタグ、品質表示、ボタン、ジッパーなどの再生するに当たって不要なものを手で切っていくといった作業が必要になります。
以前訪れたときには、パートの女性の方々がみんなで座って屋内で作業をしていました。ただ先日の訪問では、灼熱のすごく過酷な環境のなかで、おじいさんが1人でタグを切ったりボタンを取ったりしていたんです。『リサイクル素材っていいよね』とか、『これからはリサイクルされたマテリアルだよね』とか軽々しく言うけれど、でも実際は背景にこうした作業がある。背景の解像度がすごく低かったなと思いました。
これってやっぱり直接行かないと分からないことだと思うんですよね。どれぐらい暑かったかとか、埃のなかでやってるとか、おじいさんの『これやるしかないからね』といった言葉とか。本当にちょっとした会話のなかで生まれる、ちょっとした言葉使いとかから得るものがすごく大きくて、紙の上とか画面の中だけでは、こうした情報は得ることができないですよね」
工場で古着のネームタグや品質表示などの切り取りを行う/Image via eri
リサイクルウールの工場と同様に、現地に行き、ちゃんと知ることの大切さを感じた沖縄旅のエピソードも紹介したい。
「2023年3月に沖縄の基地問題や沖縄戦に関する取材に行く機会があり、新基地建設が進んでいる辺野古のゲート前で、移設反対の抗議の座り込みに参加しました。そのゲートから少し下ったところに建設用の土砂を運び出す場所があるのですが、そのゲート前でご高齢の夫婦が『牛歩』をしていたんです。ゲートを出入りするトラックの前をゆっくりと渡るという抗議活動です。
私もそこで牛歩をやらせていただいたんですが、3月とはいえ太陽は照り付けているし、トラックが至近距離に停車しているので土埃や排気ガスもあり、工事現場の管理者が『邪魔をするのはやめてください』と圧をかけてくる。私はほんのちょっとやっただけだけれど、ものすごく精神的にも辛かった。
さっきのリサイクルウールの工場の話とも似ていますが、私は基地の移設に反対だし、同様の考えを持つ沖縄に住む人たちに連帯してる気持ちで居たけれど、こうやって毎日現場で声をあげてくれている人たちの状況を体感したら、この抗議の過酷さを知らずして『反対』と言っていたのは、自分のなかでは辻褄があってなかったなって思ったんですよね」
辺野古ゲート前、移設反対の抗議/Image via eri
eriさんは沖縄で出会った老夫婦に「例えば、観光に来た人が『牛歩を30分だけ手伝いたい』といったら、短い時間お手伝いに来てもご迷惑じゃないですか?」と問いかけた。すると、「ほんとに嬉しい。その間にお水を飲んだりトイレに行ったり休んだりできるから」と返答が返ってきたという。
そうした会話を経て2024年6月、eriさん主導で未来のために活動するコレクティブ「WE WANT OUR FUTURES」は富士国際旅行社と共催で、沖縄へのスタディーツアーを開催するに至った。

ツアーは「『慰霊の日』に知る・感じる 沖縄のいま、自然、基地のこと」をテーマに、沖縄戦跡を巡ったり、現地の人と交流したりしながら、沖縄のいまを学ぶといったもの。
「みんなが沖縄のことを大好きで、『ただただ遊びにいきたい』という気持ちもわかるし、『せっかく旅行に行くのに、難しいこととか悲しいこと見たくないわ』と思うかもしれない。
けれど、美味しいもの食べてショッピングしてという旅のなかに、『今日は朝ちょっと時間あるから辺野古のゲート前に行ってみようかな』とか、その土地の歴史とか現状に一つでも触れるような旅ができたら、世界の景色は変わっていくのかなと思ったりもします。
それに、そういう旅をすると、その土地をより身近に感じたり、『好きだな』って思えたりもするんですよ」
※本取材(2024年4月)の2ヶ月強後である6月28日、抗議活動が行われていた安和港付近で、牛歩をしていた女性と警備に当たっていた男性がダンプカー左折時に巻き込み事故に合い、男性は死亡、女性は重症を負った。男性のご冥福をお祈りすると共に、どうかこれ以上傷を負う人を出さず、対話がすすむことを願っている。
ちゃんと、“見直し”たい
ここまでチェンマイ、名古屋、沖縄とeriさんの旅の話を伺ってきた。
筆者の目にはeriさんは旅を通して、頭だけでなく身体から現地の今を知り、見つめ、痛みや苦しみを感じている人がいればその状況や気持ちに連帯し、つながり、完全に一致させることはできずともそれらを自分の一部にしようとしているように見えた。
世界中で起こる負の状況を一人の力で変えられるわけではない。それでも、ちゃんと知ることで見える世界はガラリと変わり、その後の考えや行動にも変化が起きる。今を変えていく力を得るためにも、eriさんは旅という体験を暮らしに取り込んでいるのかもしれない。
しかし、全ての人が簡単に旅に出られるわけではなく、様々な事情で旅ができない人もいる。そんな人が日常のなかで旅のような体験をする一つの方法をeriさんが教えてくれた。
「私は古着を仕事で扱っているんですが、古着ってすごく想像します。『これ着てた人ってどんな生活してたのかな』とか、『どういう風に、何人の手のなかで育ってきたのかな』って。
古着は喋れないから、『誰につくられたの?誰が着てたの?どこにいたの?』とかって聞いても答えてくれないんだけど、でも確実にいるわけですよね。つくった人、着た人、売った人、手放した人、受け取った人。古着を通していろんな国の、そうした服を介した営みを感じてきました。その体験は、自分のなかの垣根というかボーダーを薄くしていってくれている感じはします」
Image via eri
ー
今回の取材の一番最初に筆者はeriさんにこんな質問をした。
「これまでした旅のなかで、印象に残っている旅を教えてください」
eriさんはその質問のあと、うーんと考え込み、一度その質問はパスすることになった。そして1時間の取材の最後にこう話してくれた。
「自分のなかで、旅を通して世界を見るためのアイテムや視点を増やしていっている感じがします。一番最初の質問に答えられなかったのは、これまでしてきた旅それぞれは、確かに一つひとつ別々のものなんだけれど、やっぱり『一つひとつがあって全部が積み重なった先がすごく大事だ』と考えているからなんだと思います」
チェンマイでの旅の話をしている時に、eriさんはよく「見直す」という言葉を使っていた。「次の景色ってどうなんだろうな、今って本当に綺麗なのかな、ちゃんと見直さなきゃ」。
「見直す」を辞書で引くといくつか意味がある。「改めて見る」「再検討する」そして「(病気や景気などが)よくなる」。eriさんの使う見直すにはその全ての意味を包括するような、「“見”ることで、“直し”たい」という想いが込められているような気がした。
旅を通して、今を、未来を、“見直し”ていく人が増えれば、世界に希望の光がさすのかもしれない。今を見つめるパワーをeriさんにまた強くもらった取材だった。
【参照サイト】DEPT COMPANY
【参照サイト】WE WANT OUR FUTURES TOUR IN OKINAWA
【参照サイト】Yahoo!ニュース/辺野古埋め立ての土砂を運ぶダンプ、抗議中の市民と警備員をひく 1人が意識不明 沖縄・名護市の安和桟橋
【関連記事】あなたはどう旅する? | 英国サステナブルトラベルの専門家に聞いた、旅の魅力
【関連記事】バリ島ウブドに旅立とう。心で ”良さ” を感じるエシカルホテル「Mana Earthly Paradise」
飯塚彩子
最新記事 by 飯塚彩子 (全て見る)
- つながりはじめる再生と対話の旅。ひろしまリジェネラティブツーリズム【レポ後編】 - 2025年2月28日
- つながりはじめる再生と対話の旅。ひろしまリジェネラティブツーリズム【レポ中編】 - 2025年2月28日
- つながりはじめる再生と対話の旅。ひろしまリジェネラティブツーリズム【レポ前編】 - 2025年2月28日
- 「ちゃんと見直したい」環境アクティビストeriさんに聞く、旅の話 - 2024年12月11日
- 思いっきり“とことん”楽しむだけで、地球や地域のためにもなる。新しい旅のスタイル「GREEN JOURNEY」始動 - 2024年8月22日