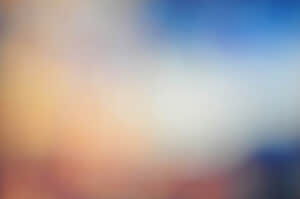晴れた空、澄んだ川、ソースの匂い、釜戸で炊いた卵かけご飯、鳥のさえずり、ふかふかの土、漆器の滑らかな口当たり、真っ暗闇、火の柱、路面電車、高層ビル、とろんとしたソフトクリーム、あの人の笑顔……。「ひろしま」という文字を見て今、筆者が思い浮かべるのはこんなものたちだ。
・
サステナブルツーリズムで世界をつなぐ旅マガジンLivhubが、一般社団法人Hiroshima Adventure Travelとの共催で2022年10月9日〜11日に開催した「ひろしまリジェネラティブツーリズム」。地域の風景、広島の物語、自分自身の3つの再生を軸にしながら、“つながりはじめる、再生と対話の旅”をテーマに広島市内中心部と広島市湯来町を2泊3日で旅した。
広島の風景や物語をより多面的にした3つの体験
前編では、ローカルガイドの導きのもと、広島の街を見つめた旅模様をお伝えした。中編では、広島の風景や物語をより多面的にしてくれた旅中の体験を3つ紹介する。
視覚以外の五感を開いて旅をする。二葉山での森林浴
「皆さん、普段五感を使っていますか?」
森林浴ファシリテーターの川口康太さん
森林浴ファシリテーターの川口康太さん(ガイドネーム:ステファン)の、そんな問いかけとともに始まったのが前編で紹介したAsageshikiツアー内の二葉山での森林浴。
人間の五感による知覚は視覚が全体の83%を占めていると言われるなかで、視覚優位の身体をそれ以外の知覚にも開いていくために、私たちはまず目を瞑った。
「どんな音が聞こえますか」
鳥の囀り、風で葉が揺れ擦れる音、遠くを通る車、聞こえていなかった音が耳に入ってくる。

聴覚が開いてきたところで、もう一つお題が投げかけられた。
「枝を持って、地面の土を掘ってみてください」
突然の投げかけに少々驚きながらも、穴を掘ってみる。数分後あたりには参加者それぞれが掘った複数の穴ができた。次に掘った穴に鼻を近づけ匂いを嗅ぐように促される。少し冷たい湿った深い香りがする。
他の場所の香りも嗅いでいく。ハーブのようなすーっとする香り、水っぽい香り、若干半径5メートル程の空間という近い距離にありながらも、それぞれに香りが異なる。土の下には水が通り、植っている木の種類や微生物の状況などによって変化が起こるという。皆が土に顔を近づけ匂いを嗅ぐ様子はクスッと笑える光景で、今も脳裏に残っている。

その後もいくつかの問いかけと共に自然のなかで五感をひとつずつ開いていき、最後には裸足になってシートのうえに寝っ転がり、目を閉じて、ただただ脱力した。

少しずつ自分と二葉山との境目が曖昧になっていく。
そのまま眠りたいほど、心地よい時間だった。参加者の表情も少しほどけたように見えた。
過去と今を未来に繋ぎ続ける広島漆芸作家から、あり方を見直すきっかけを
広島の伝統工芸と聞いて思い浮かぶのは何だろうか?声の大きな要素により見えづらくなっている部分もあるが、熊野筆や宮島細工など、広島には長い歴史を持つ伝統工芸品が複数存在する。広島市内の仏壇通りに位置する「高山清」も、大正2年に仏壇の塗師として始まってから、広島において2番目に伝統工芸品に指定された「広島仏壇」の歴史を代々繋いできた。

高山清の四代目を担う高山尚也さんも、継承当時は仏壇の製造等を主軸に活動していたが、現在では漆芸作家としても活動している。
高山清の四代目の高山尚也さん
お寺の修復時にお椀の修理を依頼されたことをきっかけに、「自分の子どもにも漆器を使ってもらいたい」と感じ、実際に作ったところ「この器で食べると美味しい」と喜んでくれたことが背中を押し現在に至る。高山さんの漆器は、2023年に行われたG7広島サミットにおいて来賓の各国首脳の贈呈品にも選出されている。
G7広島サミットにて贈呈された漆器
ツアーでは実際に工房を訪れ、高山さんにお話をお伺いしながら、漆器づくりにおいて重要な下地づくりの体験や、漆塗りの見学、漆器を用いた試飲で使い心地を体感させてもらうなどした。
漆器を手にとる参加者
「昔は物流が限られていたので木のお椀を使う人が多かったんですね。それをコーティングするために漆が使われていた。しかし、プラスチック製品や化学塗料製品の普及や生活様式の変化に伴って漆器は出番を無くしてしまいました。
漆器は長年、世代を引き継ぎながら使うことができます。『自分が使っていたお椀を、孫に渡したいから綺麗にしてほしい』と依頼されたこともありますよ。お寺の修復では400年前のものを直すこともあります。日本は資源が少ないですから、壊れたら直せるようなものづくりをしてきたんですよね」
そうした話を聞いたうえで、高山さんの作った漆器を手に取り、お茶を飲む。

高山さんのお子さんの発言の通り、長年使い繋ぐことを想定して、人の手で想いを込めて丹念に作られた器で飲む茶には温度があり、器が美味しさを高めるように感じられた。体験に感動し、自身の子どものために漆器を買い求める参加者もいたほどだ。
美しいお椀を手に高山さんは、現代の短期利用を前提とした製品づくりや生活様式に対して「あり方を見直してほしいなと思う」と口にしていた。
牛がのどかに歩く景色とともに、「食べることは生きること」と伝えるために。サゴタニ牧農の挑戦
広島市内から車で50分程のところにある町、湯来町に位置するサゴタニ牧農(砂谷牛乳)は、自社牧場 サゴタニ牧場(久保アグリファーム)を有する昭和25年から地域の人々に愛されてきた牛乳メーカー。敷地内には工房やカフェがあり、生乳を使用したジェラートを広大な牧草地を眺めながらいただけるとあって、週末には長蛇の列ができるほど人気の場所だ。
写真は濃厚な味わいのソフトクリーム
そんなサゴタニ牧農の三代目である久保宏輔さんは現在、2040年を目指して牧場内の全ての牛を牛舎飼育から放牧に切り替えるため「牛の棲む森プロジェクト」を進めている。
サゴタニ牧農三代目の久保宏輔さん
日本の牧場の牛の多くは一生を牛舎で過ごす。しかし、久保さんが思い描くのは放牧地を牛がのどかに歩き、草を食み、その牛から人間が乳を分けてもらう景色。そのために放牧地の整備や放牧で生計を立てるための計画などを日々行っている。今回のツアーでは実際に牧場を訪問し、久保さんからお話をお伺いした。
「昔ここは、雑草が生え荒れた場所でした。傾斜がありトラクターが入れず牧草地にできないので放置していたのですが、全ての牛を放牧するにはより広い放牧地が必要となるので、3年ほど前から整備を始めました。現在は20頭程を放牧で育てているのですが、牛たちをこの場所に入れることで、生態系が変わってきているのを感じています」
傾斜のある放牧予定地
「背が高く繁殖力の強い植物を牛が食べることで、草食動物が好むクローバーなどの背が低い植物に光が届き育つようになったり。牛が草を食べて、糞をすることで、糞が堆肥化したり周辺が不食過繁地になったりすることによって、土壌が豊かになり、牧草の成長を促して、放牧地の自然環境が徐々に再生されていっています」
牛を起点に動き出す自然の循環が、長い年月をかけて荒廃していた土地を豊かな牧草地へと変えていく。
草のうえで日光にあたり気持ちよさそうな放牧牛
放牧地の自然環境が徐々に回復していく様子に、久保さんは「全ては土ですね」と話す。
牧草を輸入に頼る牧場も多いなか、サゴタニ牧場では昔から自身で牧草をつくることを大事にしてきた。創業者であり久保さんの祖父にあたる久保政夫さんはこんな言葉を残している。“自前の良い土で良い草を育て、良い草で良い乳牛を育てる。酪農とは草を乳にかえる農業である” 。
お話を伺ったあと、参加者一同で放牧地を拡大するための杭打ちをお手伝いさせていただいた。

杭よりも大きな60cm程の深さの穴を堀り、電車の枕木として使われていた木材を埋めていく。「あれ、そういえば森林浴をした森でも穴を掘ったような?」と話をしながら、掘り進めるが、これがなかなか難しい。

スコップで掘るには固すぎる岩がゴロゴロ地中に埋まっていて、秋の涼しい陽気のなかではあったが8人で汗をかきながら2時間程堀り続けて、打てた杭は3本。
Photo via GutsMan
放牧地の土づくりも含め、一朝一夕で成るものはなく、「長い年月をかけることで牛乳に関わらず私たちの食は守られているのだ」と、作り手の方々への深い感謝の念を抱いた。

「祖父の時代には牛乳は栄養価の高い食品として非常に希少でした。でも今は他にも様々な食品の選択肢があって、牛乳がなくなっても一時的には困るかもしれないけど、なければないで生きていけるものになった。だからこそ僕らは、食品としての牛乳やチーズを提供するだけではなくて、『食べることは生きること、他者とのエネルギー交換である』そういった食の根っこにあることを感じられる場所をつくっていきたいと思っています。少しでも食べるものに心を寄せられる人が増えていくといいなと」
牧場運営の裏にある想いや歴史、未来のありたい姿を伺いながら、放牧地づくりのお手伝いをさせてもらったことで、筆者自身を含む参加者のなかに、観光客としての関わりではなかなか持つことのできない強度ある関係が、サゴタニ牧農との間に生まれているのを感じた。
「時間がかかるっていいことだなと思うんです。そっちのほうがつくる過程を見せることができるし、多くの人に関わってもらえるので。放牧は最初は主に僕がやりたいことだったけど、今はそうしたつくる過程のなかで自分だけの夢じゃなくて、みんなに喜んでもらえるものになってきている感覚があります」

ー
ひろしまでの旅は記事後編に続く。
【参照サイト】高山清
【参照サイト】広島漆芸作家 高山尚也
【参照サイト】サゴタニ牧場
【参照サイト】一般社団法人Hiroshima Adventure Travel
飯塚彩子
最新記事 by 飯塚彩子 (全て見る)
- つながりはじめる再生と対話の旅。ひろしまリジェネラティブツーリズム【レポ後編】 - 2025年2月28日
- つながりはじめる再生と対話の旅。ひろしまリジェネラティブツーリズム【レポ中編】 - 2025年2月28日
- つながりはじめる再生と対話の旅。ひろしまリジェネラティブツーリズム【レポ前編】 - 2025年2月28日
- 「ちゃんと見直したい」環境アクティビストeriさんに聞く、旅の話 - 2024年12月11日
- 思いっきり“とことん”楽しむだけで、地球や地域のためにもなる。新しい旅のスタイル「GREEN JOURNEY」始動 - 2024年8月22日