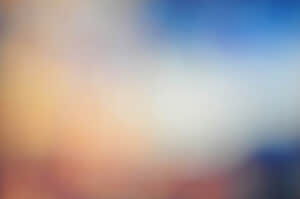image via 旅するいきもの大学校!事務局
大手や老舗企業が新規事業開発に取り組む際に、既存事業の強みをどう活かすべきか。
こうした課題に対し、クラブツーリズム株式会社は独自の解を見出している。約700万人の顧客基盤とコミュニティ形成のノウハウを武器に、観光領域を超えた社会課題解決型ビジネスを展開する同社の取り組みから、新規事業開発のヒントを探る。
この記事では、クラブツーリズムの創業からの精神を活かしながら領域横断する、クラブツーリズム株式会社の鈴木光希さんに話を伺った。
 2009年クラブツーリズム入社。テーマ旅行部門で長年「コミュニティづくり」をキーワードとした趣味の旅を担当。その後事業開発部門に異動して企業連携による新規サービス創出を担当。特に、コミュニティ形成や地域のファンづくりを軸とした事業開発に従事。最近では地域創生事業や地域のプロスポーツクラブと連携したサステナビリティ領域のプログラム開発、リジェネラティブ・ツーリズムの推進など、社会課題解決型の新規事業開発にも携わる。
2009年クラブツーリズム入社。テーマ旅行部門で長年「コミュニティづくり」をキーワードとした趣味の旅を担当。その後事業開発部門に異動して企業連携による新規サービス創出を担当。特に、コミュニティ形成や地域のファンづくりを軸とした事業開発に従事。最近では地域創生事業や地域のプロスポーツクラブと連携したサステナビリティ領域のプログラム開発、リジェネラティブ・ツーリズムの推進など、社会課題解決型の新規事業開発にも携わる。
創業理念を軸にした「コミュニティづくり」という独自ポジション
「ただの旅行会社じゃなくて、『旅』を手段にお客様のやりたいことを実現している企業なんです」
クラブツーリズムは、2004年に近畿日本ツーリストよりクラブツーリズム事業を譲受し、新会社として発足した。当時からミッションステートメントの一部に「コミュニティを育む」という言葉を掲げ、単なる旅行会社ではない独自の立ち位置を確立してきた。
クラブツーリズムの特徴は、顧客のリアルな声を反映していくダイレクトマーケティングにある。旅行冊子を直接顧客の自宅に届け、顧客の趣味嗜好に合わせたコミュニティを形成してきた。
冒頭で鈴木さんが語るように、一般的な旅行会社のプランは、ハワイや京都、北海道など「旅の目的地」を中心に旅を組み立ててることがベースにあるが、クラブツーリズムのコミュニティ型の旅行では、「歴史」「写真」「まち歩き」など、顧客がやりたいことや嗜好性に合わせ、旅という舞台装置を使って実現するのがクラブツーリズムのビジネスモデルの1つの特徴だ。
現在、クラブツーリズムは約700万人の顧客を持ち、この膨大な顧客基盤と長年培ったコミュニティ形成のノウハウが、新規事業展開における最大の強みとなっている。
観光業との偶然の出会いから新規事業開発の起点へ
「入社試験を受けていたのはメディア系企業ばかり。学生の頃はクラブツーリズムという企業も知らなかったくらいです」
2009年にクラブツーリズムに入社した鈴木さんだが、当初は旅行業界への強い興味はなかったという。ただ何となく受けた入社試験で感じた魅力がその後の入社に繋がっていくことになる。
採用決定後、クラブツーリズム主催のツアーを経験せずに入社するのもどうかと思い、両親を連れてこっそりとシニア向けバスツアーに参加。そこで目にしたのは、ツアー参加者の異様な盛り上がりだった。その出来事をきっかけにさらにクラブツーリズムに興味を持ち、旅行業界へ飛び込むことを決意したのだという。
入社後最初に配属されたテーマ旅行セクションで、「歴史の旅/歴史街道あるき旅」や「写真の旅」を担当した鈴木さんは、長い年月をかけてツアー参加者との間に築き上げた密な関係性とニーズのヒアリングを通じて、旅行事業の可能性を再発見する。特に、デスティネーション主導の従来の旅行業とは異なり、コミュニティを起点として、後からデスティネーションを組み合わせる新しいアプローチを見出していくことになる。
クロスセクター型ビジネスモデルの構築
「クラブツーリズムがずっと旅の中で実践してきたコミュニティづくりの手法を使えば、旅以外の領域でも同じことができるんじゃないかと思っていました」

この気づきが、後の新規事業開発における重要な起点となる。既存事業で培った強みを別の文脈で活用するという発想は、大企業における新規事業開発の王道でありながら、実践は容易ではない。鈴木さんはその実践者として、社内では遊軍的な働き方をしながら橋渡しをしていくことになる。
鈴木さんはその後、テレビ東京ダイレクト社との共同事業による旅の通販番組立ち上げや、大手通信キャリアとの協業によるオンラインサービス「クラブツーリズムパス」の立ち上げなど、事業領域を拡大していく。
さらに、イオンタウン社との協業による地域コミュニティスペースの運営など、旅行業の枠を越え、まちづくりや地域活性化への展開をスタートした。これらの取り組みに共通するのは、クラブツーリズムが持つコミュニティ形成のノウハウと、パートナー企業が持つ強みを掛け合わせる「クロスセクター型」のビジネスモデルだ。
島根県江津市での取り組みでは、テレビ東京社との連携により番組を通じた地域課題ソリューションに挑戦し、番組を通じて集まった都市部の様々な企業や現地の事業者の方々と共創関係を築き、JR線の無人駅舎の利活用(地元クラフトビールのブルワリーに)や広大な公園の利活用プロジェクト、市が公認の公式プログラムや体験ツアーに参加することで公式の観光大使になれる制度(GOTSU CREW制度)を番組を通じて立ち上げた。地域とゲスト間の持続的な関わりを創出し、継続的な関係を持つファンを生み出すことに成功した。この事例は、観光と地域創生を融合させた新たなビジネスモデルとして注目を集めている。
長野県生坂村での社会課題解決型プロジェクト
「自分も含めた環境課題に強い関心がない層に、どう『ネイチャーポジティブ』というテーマに関心をもたせるかが課題でした。少し語弊があるかもしれませんが、今回の試みを極端に言うと『ネイチャーポジティブのエンタメ化』だったのかもしれません」
長野県のちょうど真ん中に位置し、松本駅から車で約50分ほどの場所にある長野県生坂村。ここは環境省の脱炭素先行地域に指定されていて、現在「ネイチャーポジティブ」をテーマにした新しい地域活性化の形を模索している。「ネイチャーポジティブ(自然再興)」とは、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せることを意味する。
この生坂村を舞台に、鈴木さんを始めとしたクラブツーリズムと地元のJリーグクラブでもある株式会社松本山雅、地元の事業会社の合同会社HiTTiSYO、その他に株式会社フューチャーセッションズ ・株式会社大広の5つの企業が連携したプロジェクトチームは、「何度でも訪れたくなる里山づくり(第2のふるさとづくり)とネイチャーポジティブ」をテーマにした6回シリーズのプログラムを実施。
ちなみにこのプログラムは講義やセミナーだけではなく、地域の方も交えた竹林整備や野生生物の生態観察などの現地フィールドワークなど、体験型のプログラムを多く取り入れることで、参加者が楽しみながら地域に対する理解と愛着を徐々に深められる設計になっている。
この「旅するいきもの大学校!」を通じて、約50人ほどの参加者が自発的かつ継続的に村を訪れ、山間部や農村地域の遊休地や耕作放棄地を活用し、地元住民との交流を通じて再生していく仕組みを構築した。
このプログラムを終えた参加者は、村公認の「生坂村公式自然研究員」に認定され、その後も継続的に生坂村に関わり続けることになる。このプロジェクトチームと生坂村の地域の人々はこの仕組みを通して、単なる観光地づくりではなく、持続可能な地域づくりを目指している。ちなみにこの取り組みは、観光庁が主催した「第2回サステナブルな旅アワード」特別賞も受賞した。
コミュニティをつくるプレイヤーとして地域と関わる
「旅行ってやっぱり地域を盛り上げるもの。僕たちはクラブツーリズム株式会社のコミュニティサービスで地域を盛り上げたい」
クラブツーリズムは、旅行会社としてではなく、コミュニティを作るプレイヤーとしての確固たる地位を目指している。ブレずに創業時から掲げてきた「コミュニティづくり」という概念を、現代のニーズに合わせて進化させながら、社会課題の解決に取り組んでいる。
取材終了後、移動しながらの雑談の中でも、鈴木さんの頭の中には今後を見据えたプランとアイデアがふつふつと湧きあがっているようにも感じた。
新規事業開発者が持つべき領域横断のマインド
鈴木さんの取り組みからは、新規事業開発者が持つべきマインドセットとして以下の点が浮かび上がる:
- 既存事業の本質的な強みを再定義する視点
- 異なる文脈での応用可能性を常に探る好奇心
- 社会課題と事業機会を結びつける発想力
- 異業種との協業を推進するオープンマインド
- 創業理念を大切にしながらも、時代やニーズに合わせて進化させる柔軟性
既存事業の強みを活かしながら、社会課題解決という新たな価値創造に挑戦するクラブツーリズム。その取り組みは、大手企業における新規事業開発のあり方に一つの指針を示している。重要なのは、自社の強みを再定義し、それを異なる文脈で活用する発想力だ。
企業と個人、都市と地域、旅と暮らし。社会にはさまざまな領域や分断があるが、つきつめれば同じようなところに辿り着くこともある。世の中が求めるものをつぶさに観察してその解を丁寧に積み上げれば、その壁を越境する扉がひらけてくる。今回の鈴木さんの数々の言葉は、そんなマインドを教えてくれている気がする。
【参照サイト】クラブツーリズム株式会社公式サイト
【参照サイト】旅する生きもの大学校!公式サイト
いしづか かずと
最新記事 by いしづか かずと (全て見る)
- 「いってらっしゃい」と「おかえり」を繰り返す、隠岐の循環をたどる旅路。Green Academyツアーレポート後編 - 2025年9月18日
- 「いってらっしゃい」と「おかえり」を繰り返す、隠岐の循環をたどる旅路。Green Academyツアーレポート前編 - 2025年9月18日
- 茅ヶ崎でコーヒーと本を片手に”まちの日常”にふれる。分散型まち歩きコーヒーフェス「Takasuna Greenery Coffee Festival vol.4」初の2日開催! - 2025年4月30日
- 領域を越境するクラブツーリズム株式会社。コミュニティづくりで切り拓く新規事業の可能性 - 2025年3月4日
- 奥会津のローカル線沿線で、自然と共生する暮らしを体感。暮らすように旅する「奥会津ワーケーション」の魅力 - 2025年2月24日