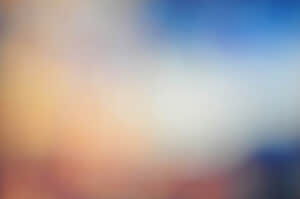なぜ森に入ると気分が良くなるのだろうか?
都会の生活では絶え間ない雑音やせわしなさに圧倒され、ストレスや疲労を感じることがある。自然の中に身を置くことで、精神の平穏とバランスを取り戻すことができる。森の中で過ごすことは特に効果的であり、心身両面に恩恵をもたらす。
森林浴愛好家にとって、森林浴が気持ち良い理由は明らかだ。森林浴とは、森林の中で自然とのつながりを意識しながら感覚を働かせることで、心身ともにリラックスする方法だ。それはもちろんプラシーボ効果で気分を高揚させるために森で時間を過ごすことではない。
森林浴は、科学的根拠に裏付けられた健康効果がある。 森林から放出されるフィトンチッドは、免疫機能を向上させ、ストレスを軽減し、精神的な健康を増進する。 森林浴では、これらのフィトンチッドを吸収し、五感をすべて開放して自然と再びつながることで、健康状態のバランスを整えることができる。森林の音、例えば川のせせらぎや野鳥のさえずり、そして森林の芳香は、アロマセラピーのような効果をもたらし、心身両面に恩恵をもたらす。

赤沢自然休養林でのツアーの様子。森林セラピーを希望する来訪者は、森林で過ごす前と後に血圧とコルチゾール値を測定し、改善を視覚化することができる(画像:Roger Ong)
しかし、森の中で過ごすと気分が良くなる理由について、「完全な答え」にまだ到達していないとしたら? 気分が良くなるだけではないとしたら? この答えは、「一般社団法人森と未来」の視点から見えてくる。
一般社団法人森と未来と巡る、森林浴の核心
一般社団法人森と未来(代表理事:小野なぎささん)は、10月14日から18日にかけて「Japan Shinrin-yoku tour 2024」を開催した。このツアーは、森林浴愛好家を各国から招き、日本の森林で森林浴の真髄を体験・発見してもらうという、非常に意義深いものとなった。
森と未来は、森と人が共に持続可能な未来を創造することをビジョンに掲げ、2015年に設立された。彼らは、日本の森林が健全に成長し続けるためには、企業、地域社会、個人など、あらゆる人が森林に関心を持ち、現代にふさわしい森林との関わり方を見つけ、森林の活用を推進していく必要があると考えている。
また、このツアーは、米国発祥のAssociation of Nature and Forest Therapy(ANFT)のガイドと日本のShinrin-yoku facilitator®︎が国境を越え森林浴を体験する学びの交流でもあった。
参加者はアメリカ、カナダ、ニュージーランド、シンガポール、スロバキアなど、さまざまな国から集まり職業も様々。例えば、子供の精神的な健康をケアする医療専門家、都市部に自然を取り入れようとする造園家、より多くの人に森林浴を体験してもらおうと志す森林セラピスト、自然からインスピレーションを得ようとする芸術家など。ある意味では、参加者たちは皆、森との関係を深める巡礼者だったともいえる。
ちなみに「森林浴」という言葉は、1982年に日本の林野庁によって提唱された。しかし、日本と森林との関係は、この近代的概念が生まれる何世紀も前から続いている。古代の日本人にとって、森に身を置くことは単なる治療ではなく、その文化の根幹をなすものだった。森は日常生活に欠かせないものであり、自然のあらゆる側面への畏敬の念を強調する神道から、食料や生計、自然からインスピレーションを受けた感情や才能をたたえる俳句のような文化に至るまで、あらゆる面で重要な役割を果たしていた。
自然とのつながりが断たれていることが、ストレスや気候危機などの社会問題や環境問題の一因となっているという点で、ツアーの参加者は皆意見が一致していることに気づいた。
おそらく今森林浴は、自然とのつながりを取り戻し、これらの課題に対処する手段となり得る。このツアーでの森林浴のシンプルな体験は、森と未来の指導により、やがて意義深い変化をもたらす力としての潜在的可能性を実感するものへと変わっていった。
森は私たちに何も求めない ― 森と私たちの関係
しかし、そのことについて語る前に、人類文明の過去と現在の森との関係性を評価する必要がある。私たちは、森が私たちに酸素を提供し、数百万もの生態系に棲家となる場所を提供していることを当然のこととして受け止めがちだが、森は自然界における完璧な二酸化炭素吸収源でもある。

一般社団法人「森と未来」代表理事の小野なぎささん(写真:Roger Ong)
ツアー初日、参加者は長野県上松町に移動し、そこで「森と未来」の小野なぎささんからツアーの概要が説明された。上松町観光協会の松原和枝さんからは翌日訪れる予定の森についての概要を説明してもらった後、小野さんからは日本の森の現状について話を伺った。小野さんの話の核心部分では、以下のような日本人と森の関係についての興味深い示唆があった。

時差ボケの影響を受けながらも、参加者は日本の森への好奇心を抑えきれない様子(画像:Roger Ong)
「歴史的に見ると、木材は燃料としてだけでなく、家具や浴槽など、古代の日本の日常生活の基礎を成すものとして使用されてきた。家屋は柱から襖、畳に至るまで、すべて木材でできている。森林は、野菜やキノコ、動物の肉(さらにはきれいな水まで)といった食糧も私たち日本人に恵んでくれていた」

地元の人々の料理に欠かせないナメコは、森の中でたくましく育つ(画像:Roger Ong)

柱から棚、扉、床に至るまで、日本の大工の技術は金属の釘を必要とせず、森に大きく依存して日本の家屋を建てました。
「森はまた、多くの人々の生計を支えていた。林業以外にも、森が与えてくれる恵みを活用する職人たちが生まれ、漆の木は漆文化を生み出した。ハゼの木の実から、職人たちは和ろうそくを作った。和紙は昔から広く使われており、その原料は木から生み出される。職人たちは、人間も自然の一部であり、自然から切り離された存在ではないことを最もよく理解していた」

漆の木は、日本に漆器の文化をもたらした
私たちと森との断絶
残念ながら今日においても、私たちが自然と断絶していることは事実であり、私たちは森を当然のものとして受け止め、生活に欠かせない一部であるという事実を無視しがちだ。「Plant Blindness(植物失明症)」という用語は、人々が身の回りの植物を見落としている現象を説明する際に使用される。これは、植物の多様性や生態学的重要性に対する認識や評価の欠如が広く見られることを強調している。その結果、食糧安全保障などの問題への取り組みが脅かされ、解決策としての自然保護が直感的に理解されなくなっている。
日本の森林も十分に活用されていない。その原因は、森林が十分に評価されていないからだ。日本では先人たちが大規模な森林再生に取り組んだ結果、国土の68.5%が森林に覆われ、森林被覆率はOECD加盟国中3位となっている。にもかかわらず、日本の木材自給率は2023年時点で42.9%にとどまっている。日本の木材が過小評価されているため、林業は財務的な持続可能性に問題を抱えている。そして現在、多くの森林が放置され、劣化が進んでいる。

放置林(左)は、暗い雰囲気があるが、逆に整備林(右)は生き生きと感じられる(画像提供:一般社団法人森と未来)
また、森林との不安定な関係において、人間が有害な存在であることも分かった。アマゾンの熱帯雨林における違法伐採からコンゴ盆地での採掘や密猟まで、人類は土地や資源を目的とした大規模な森林伐採により、森林を乱用し、劣化させてきた。IUCN(2024年)のレッドリストは最近、絶滅危惧種リストを更新し、絶滅の危機に瀕している樹木の数は、絶滅の危機に瀕している鳥類、哺乳類、爬虫類、両生類の総数を上回っている。
自然から離れることは、環境問題にとどまらず、私たちの精神的な健康にも影響を及ぼしている。都市生活の利便性と引き換えに、私たちは心の健康を犠牲にしているかのようだ。日本では、2005年には3万人以上も自殺者が増加し、従来の医療に代わるセルフケアとして、全国のさまざまな森林で森林セラピーが導入されるようになった。
つまり、誰もが制約なく享受してきた森林に人間が感謝するという状態から、多くの人々の生活の中で森林が脇役になってしまったという変化が見られる。私たちはどのようにして森林や自然とのつながりを失ってしまったのか?その間に失われたもの、得たものは何だったのか?
森と未来と森林浴ツアー参加者は、その答えを見つけるために、次に森林浴発祥の地である長野県を訪れた。
森林浴発祥の地 – 日本の森と核心
ツアー2日目には、国有林の赤沢自然休養林を訪れた。赤沢自然休養林は、日本三大美林のひとつである木曽ヒノキ林があることから、1970年に日本で最初に自然休養林と指定され、遊歩道や森林鉄道など、来訪者を受け入れるためのインフラが整備されている。また、この地域は1982年に森林浴を推進する初のイベントがこの地で開催されたことから、「森林浴発祥の地」とも呼ばれている。

赤沢自然休養林にてツアー参加者を迎える上松町観光協会の松原和恵さん(右側のオレンジ色の服)(画像:Roger Ong)

グループに分かれて森に入る前に準備体操(画像:Roger Ong)
ここでは3チームに分かれ、地元赤沢の森林ガイドとShinrin-yoku facilitator®︎がついて森を歩いた。グループごとに参加者が自己紹介をした後、地元ガイドたちが森の小道を案内し、森の特徴的な植生について説明してくれた。ここの森はフィトンチッドの含有量が多く(通常の森の6倍!)、森の探索を快適にしてくれる。
高く伸びた木々の梢が私たちを包み込み、穏やかな気持ちと活力を与えてくれた。日本のShinrin-yoku facilitator®︎は、視覚だけでなく、五感を使って森とつながる方法も教えてくれた。例えば、土の香りを嗅ぐことで、そこに生きている100億もの微生物の存在を感じることができる。続いて参加者たちは森の中で日光浴も楽しんだ。これは、森と未来では「森ぼっこ」と呼ばれるアクティビティだ。

小さな穴を掘るだけで、土の香りが立ち込めてくる(画像:Roger Ong)

赤沢自然休養林(画像:Roger Ong)

マットの上で森林浴。森林浴に費やす時間がいくらあっても足りない位の心地良さ(画像:Roger Ong)
地元の赤沢森林ガイドたちは、ツアー参加者に対して赤沢自然休養林に関する知識を熱心に披露し、日本人が木々に対していかに敬意を払っているかを教えてくれた。多くの人が「森林浴は生き方そのものだ」と言うが、その言葉が何を意味するのかを理解し始めたのは、ここからだった。つまり、森林浴とは森林から生まれた文化的なアイデンティティであり、そのアイデンティティは神道に深く根ざしている、ということ。

地元のガイドが樹齢400年のヒノキの木を紹介。この木は伊勢神宮にも使われているものと同じ種類である(画像:Roger Ong)
神道と1000年にわたる森への敬意
神道は、自然の中に精霊や神々が宿ると信じる土着の精神伝統であり、単なる宗教ではなく、自然に深く根ざした文化だ。 これは特に森に関して顕著となっている。地元の赤沢森林ガイドは、赤沢自然休養林が伊勢神宮にとっていかに重要であるかを教えてくれた。
三重県にある伊勢神宮は、神道が日本全国に広がり始めた発祥の地であることから、多くの日本人に愛されている神社となっている。約1300年前(西暦690年)に、神道の三種の神器の一つを収める正殿をはじめとする周辺の様々な神社で式年遷宮の儀式が始まった。この儀式は20年ごとに社殿を建て替えるもので、現在まで続いている。これは伊勢神宮の式年遷宮の儀における「常若(とこわか)」の思想を体現したもので、絶え間ない更新を通じて本質を維持しようとする考え方だ。

伊勢神宮の社殿のひとつ。左側の立ち入り禁止区域がが次の建て替えの場所となる
式年遷宮の儀式での神社の再建に使用される木材はどこから来るのだろうか?伊勢神宮での「近年」とは、300年前のことで、木曽地方のヒノキが神聖な儀式に使用されることが天皇によって宣言された。そして、そのプロセスは、開始(木の選定)から完了(再建)まで、解体に至るまで、非常に厳格な儀式によって行われ、その中心となるテーマは「敬意」である。
木が伐採される前日に、彼らは木を制御された方法で燃やす。この行為は木を強化するだけでなく、木やその周辺に生息する生物や動物たちに、その木が間もなく伐採されることを知らせ、立ち退くよう警告する意味もある。
「伐採」という言葉もここでは適切ではない。木を「伐採」や「伐倒」するといった表現は使われず、代わりに「木を休ませる」という表現が使われる。この表現は1000年以上前から使われており、現在でも使われている。
そして木を休ませる方法も独特だ。三つ紐伐り(みつひもぎり)と呼ばれるこの方法は、3人の木こりが3方向から斧を慎重に振り下ろし、木材が安全に倒れるようにする。この作業には1時間ほどかかるが、敢えてチェーンソーのようにスピーディーで無思慮な伐採ではなくすることで、命を頂くことへの最大限の敬意を表している。また、木を無駄なく使うという誓いも、この敬意の裏に込められている。この作業の様子は、次の動画(約19分の位置)で、上松町観光協会が撮影したものを観ることができる。
続いて木を休ませた後には運搬が行われる。この祭りは「御神木祭」と呼ばれている。貴重な原木を運搬するために、昔からさまざまな方法が用いられてきた。特に重要な原木の場合は、鉄道やヘリコプターが使われた。かつて伝統的な方法では、森を流れる赤沢川から原木を浮かべ、川を使って運搬していた。運搬する原木に感謝の気持ちを込めて歌が歌われ、敬意と喜びの雰囲気が漂っていた。ツアー参加者として、私たちも幸運にもこの古式ゆかしい歌を体験することができた。森に響き渡る歌声は、多くの人の心に響いた。

かつて木材を運搬するために使われた川(画像:Roger Ong)
解体された古い神社の木材は廃棄されることなく、再利用のため伊勢神宮境内の他の神社や県外の関連神社に分配される。これらの神社の中には、かつての神木を祀り続けているところもある。
この敬われるべき文化は、1000年以上もの間、世代から世代へと受け継がれてきた。この文化は人々を結びつけ、森への敬意を保ち続けている。しばしば神道が日本人の心のよりどころと見なされるのもまったく不思議ではない。それは、敬意を基盤とする人間と自然の素晴らしい調和を表しているからだ。

木のチップが歩道にまかれているのは、柔らかい地面を歩く来園者の快適さのためだけではなく、木の根を守るためでもある。 地元の学生ボランティアが木のチップをまいており、この活動が若い世代の森林の未来への関心につながっている (画像:Roger Ong)
森を知ることは、地域の記憶とつながること
木曽地方と赤沢自然休養林の木々に関する物語は、その地域や国の文化にとって神聖なものであることを示している。 つまり、異なる森林には異なる歴史的・文化的影響があるということだ。
翌朝、ツアー参加者が日和田高原の森を訪れた際には、まさに「異なる森林には異なる歴史的・文化的影響がある」という例が当てはまった。池の神が短い霧雨を降らせ、日和田高原の森は深い緑色に輝いていた。しかし、参加者はすぐに濡れていたことすら忘れ、森の静寂で精神的な雰囲気を味わっていた。参加者一行に日本のShinrin-yoku facilitator®︎も合流し、彼らの専門知識をお互いに共有しました。また、ファシリテーターたちはここで、土地の記憶を引き出す方法を再び実演した。

白竜神社前の日和田高原の森に親しむ(画像:Roger Ong)
素人の私にも、日和田高原の森が赤沢自然休養林とは違うことがすぐに理解できた。この森は、日本人の多くが霊峰と崇める御嶽山(おんたけさん)のふもとに位置している。ここで私たちは、「畏敬の念」という大切な概念を知った。
畏敬の念とは、「畏怖の念」と訳すことができる。かつてこの地域に住んでいた日本人は、自分たちが自然の一部であり、自然の影響を簡単に受ける存在であることを理解していた。この地域は標高が高く、冬は厳しい寒さに見舞われる。住民たちはその危険性をよく理解しており、寒さを侮れないものとして捉えていた。しかし、この地域の気候は、多種多様な樹木や食料をもたらすなど、多くの恵みももたらすことも理解していた。畏敬の念、敬意、そして驚嘆の念のこの組み合わせが、人間と自然の共存の基盤を形成している。
つまり、森は単なる場所ではなく、森と共存しながら、自分たちよりも大きな存在として畏敬の念を抱いてきた人々の記憶を宿す場所だということ。これらは、森林浴を通じて解き放たれる、その土地の深いつながり、歴史、文化なのだ。そして、日和田高原と赤沢自然休養林の両方の森で、ファシリテーターは私たちに宇宙的な視点を与えてくれた。

日和田高原の森。赤沢自然休養林とは異なる雰囲気(画像:Roger Ong)
森林浴のさまざまな側面
「森と未来」は、私たちが日本の森林に入るとき、森林浴というものが、愛と敬意を持って森林とつながり、地域の文化とつながるための架け橋となり、私たちに大きな生態系の中での自分の役割についての視点を与えてくれることを示してくれた。しかし、森林浴は世界中で同じなのだろうか?

高山市でさらに多くの日本のファシリテーターが合流、ここで簡単な自己紹介(画像:Roger Ong)
3日目、私たちは高山市に到着し、残りの日本のShinrin-yoku facilitator®︎がツアー参加者と合流した。ツアーは次の段階へと進み、日本とその他の国々のファシリテーター間の交流を学ぶ時がやってきた。高山市の職員による歓迎の挨拶の後、ANFTガイドおよびプログラムのビジネスディレクターであるジャッキー・クァン氏が、ANFTの森林浴へのアプローチについてプレゼンテーションを行った。

ANFTのジャッキー・クァン氏が、関係性に基づく森林療法について説明(画像:Roger Ong)
「ANFTは、自然と人間との間に心を中心とした関係を育むことを信条としています。ANFTの森林浴へのアプローチにおける主な特徴は、心の知能(Heart Intelligence)にアクセスするプロセスです。ANFTの創設者であるエイモス・クリフォードは、私たちが持つ心の知能を十分に活用するために、ANFTの『Relational Forest Therapy (関係性森林セラピー)』のStandard Sequence (スタンダードな手順)を開発しました。この手順は、私たちを取り巻く世界との関係性を明らかにし、私たち自身のより深い部分を目覚めさせることを目的としています。このステップは、参加者が希望した場合のみ実施されるという意味で、意図的に「招待」であり、義務ではありません。
Standard Sequenceは『Pleasure of Presence (存在の喜び)』から始まり、自己の心、感情、身体への気づきをもたらし、次に『Notice What’s in Motion (動きの中にあるものに気づく)』 段階へと進み、参加者が自分にとって必要なものを発見するよう促します。 参加者は次に、コミュニケーションを取る対象として『森の中の存在』を選ぶことになります。例えば、参加者が何らかのつながりを感じた木や岩などです。これは『パートナーシップ』に似ており、言葉を使わずに、あるいは他の感覚を通して聞くなど、感覚が重なることで成立します。
次に、個人の内側で何が起こっているかに注目しながら、共有を行います。参加者はその後、『Sit Spot (座る場所)』を選び、内面の調和を考える時間を持ちます。最後に、茶会でセッションを締めくくります。セッション終了後、数日後、数ヵ月後であっても、自然とのつながりを再び感じたいという思いから、散歩に出かけることもあります」
クァン氏はまた、過去の参加者がこのRelational Forest Therapyの散策中に深い個人的なつながりを築いた例も紹介した。
「その成功の一因は、ガイドがファシリテーターとして、参加者が結果を期待することなくオープンな体験ができるよう促すことにあります。参加者が何とつながったのかという人間的な体験に焦点を当てるため、例えば『体験はどうでしたか?』ではなく『何に気づきましたか?』と尋ねるなど、言葉遣いにも気を配っています」

プレゼンテーションの後には、参加者全員が親睦を深め、森林浴に対する個人的な動機を共有する時間が設けられた(画像:Roger Ong)
森林浴のアイデアの国際交流
ツアー4日目には、同じ飛騨高山の清見の森を訪れた。ここもまた、これまでに訪れた2つの森とは異なる場所だった。この森は標高の高い場所にあり、私たちが集まった場所は地元の人々によって管理されており、子供たちのための自然教育プログラムにしばしば利用されていた。歴史的に見ると、この森は飛騨地方の人々の生活基盤を形成しており、現在でも職人たちが家具を作るために木々を利用している。私たちは、この森が季節のオレンジ色で地域を彩る準備を始めているのを目にした。

清見の森(画像:Roger Ong)

小野なぎささんが参加者に「コモレビキャッチ」という、深いメッセージ性のある日光キャッチの楽しいエクササイズを教えているところ(画像:Roger Ong)
ここで小野なぎささんは参加者に対し、特定の対象者を想定し、人間と森が共存できるような森林浴プログラムを考案することについての課題を与えた。ただしこの課題では、結果よりもプロセスに重点を置くよう求められる。このセッションの目的は、ANFTのガイドとShinrin-yoku facilitator®︎が交流し、両者の手法の違いや強調する点を発見することだった。
すぐに、各グループは、ストレスを抱える人々、高齢者、車椅子利用者などを対象グループとして設定することができた。ANFTのメンバーは、その後、素早いブレインストーミングを行い、参加者の感覚を森に向けさせる素晴らしいアイデアや、人と木々とのつながりを回復させる効果的な方法について意見を交わした。そこでは視覚以外の感覚を活用したり、個人的な思い出と結びつけたりするアイデアなど、創造性が議論全体に浸透しており、喜び、動き、そして仲間意識が感じられた。

アイデアを試し、楽しみながら! (画像:Roger Ong)
日本のShinrin-yoku facilitator®︎たちは、議論を地域の文化や歴史と絡めるようにしていた。高山市のファシリテーターの一人は、地元の人々がかつてどのように雪を伝え、食料を森林に頼っていたかなど、森林文化について共有していた。また、別のファシリテーターは、森林に生息するさまざまな植物の種類について共有し、参加者はその触感や香りを楽しんだ。地元の人々が森を愛し、森と共存していることを知り、参加者の皆が満足感に浸り、森が私たちに与えてくれる恵みに感謝の気持ちを抱いた。

与えられた課題以外にも、参加者は地元の文化について学ぶことができた(画像:Roger Ong)
参加者は皆、与えられた課題に的確に取り組んでおり、お互いに森林浴セッションにどのように取り組んでいるかを直接学ぶことができた。森林浴の方法はそれぞれだったが、海外と日本の森林浴が相互に補完し合うものになっていた。
例えば、ANFTのガイドは参加者の感覚を内なる共鳴へと開放するために創造性を発揮し、一方、日本のShinrin-yoku facilitator®︎はその土地の記憶と関連づけた体験を提供していた。日本のShinrin-yoku facilitator®︎は、自身のスキルアップが必要だと感じていたが、一方でANFTのガイドは、日本人が自然を尊重する姿勢は変える必要がないと話していた。

森に抱かれながら、セッションから学んだことを話し合います(画像:Roger Ong)
還元と再生 - 森林浴の豊かな可能性 –
森林が共通項であるとはいえ、森林浴の実施方法については、国によって異なる概念がある。日本は自然と文化への敬意を示し、米国は自然との個人的なつながりにおける多様性を認め、スウェーデンは「外」との交流を当たり前のものとするFriluftsliv(フリルフトスリブ)という概念を持ち、ドイツには瞑想の実践としてのWaldeinsamkeit(ヴァルデインザムケイト)がある。
森林浴のやり方について「正しい」という見解を求めるのは、建設的な議論とは言えないだろう。この森林浴ツアーで学んだように、森林浴は柔軟な性質を持っており、多様なグループに対応でき、森林資源や参加者のニーズに応じて調整が可能だ。
しかし、森林浴が何をもたらすかという問いには、壮大なビジョンが浮かび上がる。それは、自然に還元する再生可能な生き方だ。

赤沢自然休養林の背の高いヒノキ(画像:Roger Ong)
森と未来によるShinrin-yoku facilitator®︎養成講座のカリキュラムを参照すると、Shinrin-yoku facilitator®︎とは「森林浴を通じて、森林や地域社会、関わる人々がより良い状態になるよう導く人」と定義されている。
つまり「森林、地域社会、関わる人々を助ける」という点が、日本の森林浴の核心となっている。それは自然から受け取る恵みに感謝し、それを森林や地域社会に還元するという考え方になる。私たちは、同じ精神を受け継ぎ、自然とすべての人に利益をもたらす森林管理を行う「神道モデル」をそこに見た。
「森と未来」のShinrin-yoku facilitator®︎養成講座では、受講者は森林浴プログラムの企画プロセスや森林の特徴、森林浴が心身の健康に与える影響について学ぶだけでなく、その地域特有の自然環境の問題や地域の生物多様性、歴史や地域社会とのつながりについても学ぶ。 また、ファシリテーターは地域社会との積極的な協力関係を築くよう努めている。そこから、参加者はファシリテーターから学び、森と共存する地元の人々に恩返しをする機会を得る。さらに重要なのは、彼らが森をより健康で豊かにすることに貢献できるということだ。
Shinrin-yoku facilitator®︎は、単に森林浴のセッションを行う以上の大きな役割を担っている。また彼らは、森と地域社会をより良くする大きなシステムの中核を担う存在でもある。つまりShinrin-yoku facilitator®︎は、森林浴の可能性を広げている。その「可能性」とは、森林浴を通じて森林が私たちに何をしてくれるかという意味だけでなく、森林のために、そして森林を大切に思う人々のために、私たちに何ができるかという意味でもある。

日本のShinrin-yoku facilitator®︎チーム(画像:Roger Ong)
森林との再生可能な関係
上で述べたことが、森と未来が森林浴を単なる個人の健康増進や治療以上のものとして捉えている理由となっている。森林浴は、地域経済に貢献するために地元の森林を活用する地域社会への解決策も提供する。最終的には、森林の価値を高める好循環を生み出すことになる。
例えば、森林浴は国内外の観光客にとって森林を魅力ある観光スポットとしてアピールし、その地域への関心を高め、関係を構築する(つまり、関係人口を育成する)ことができる。そうした関心は地域の経済成長を促すことになる。
その結果、地元住民は森林を活用して、さらに魅力的な森林にしようという意欲が湧いてくる。それは、地元産の木材をベースにした製品開発や、地元の料理に森林の食材を活用するといった形をとるかもしれない。これらの活動は、森林を保護し育成するという意思を明確に示すものであり、ハイカーや観光客、企業など、森林に関心を持つすべての利害関係者に恩恵をもたらす。またこの再生サイクルは森林を成長させ、森林の価値を高め、地域経済に利益を生む。二次的な利益としては、土壌が強化され、土砂崩れなどの自然災害に強くなることが挙げられる。
そして、この再生の関係が日本ではどのようなものになるかを示す例がある。その一例が広島県のAsageshikiツアーだ。このツアーでは、二葉山での森林ハイキングを企画しており、その収益の一部は山の森林の維持管理に充てられる。ハイキングを楽しめるよう、当初はガイドグループが中心となって登山道の整備を行っていたが、やがてさらに発展した。Asageshikiツアーでは、日本のものとは異なる宗教の聖遺物が安置され、平和を祈るために建てられた平和塔にも訪れる。ツアーガイドは山頂で森林浴も実施し、参加者に対し森や地域の歴史を解説する。最後に、オプションで用意された朝食を楽しみ、日本茶の野点で締めくくる。

朝ヨガで森林浴体験(画像提供:Asageshiki)
さらに長野県にもう一つの例がある。それは生坂村が推進する里山再生プログラム「旅する生きもの大学校」だ。里山とは、人間居住地と管理された自然環境の調和的な共存を表す、日本の伝統的な景観だ。このプログラムでは、生物の本質について学び、体験を通して自然に関する知識を習得することができる。これらの活動には、自然調査、生態系の復元活動、地元住民との交流などが含まれる。その狙いは、周辺の土地と深い関係を築き、参加者に「生坂村」を第二の故郷として感じてもらうことだ。

生坂村の「旅する生きもの大学校」(画像:tabisuruikimono.com)
結論:なぜ森に入ると気持ちが良いのか?
webメディア「Zenbird」では、江戸時代の循環型経済(サーキュラー・エコノミー)についてよく話題にする。これは、当時世界最大の都市を2世紀以上にわたって持続可能なものにした、日本の完成されたサーキュラー江戸ノミーモデルだ(江戸時代の経済モデル)。古代の日本が循環型経済モデルを完成させることを可能にした多くの基盤のひとつは、人間は自然の一部であるという哲学を理解するだけでなく、実践することだった。そしてそもそも人間と自然は、別々の存在ではない。
私たちは森に入ると気分が良くなるが、それは生理学的にも心理学的にもポジティブな効果があるからだ。しかし、古代の日本人は森との関わりの中で、精神に宿る高揚した喜びを感じていた。彼らのライフスタイルや生業が森と密接に結びついていただけでなく、森の手入れに達成感を見出していたのだ。
こうしたことは、輪伐林業の維持、心に響く儀式の伝承、そして将来の世代のために森を大切に育てるといった、敬意と配慮に満ちた形となって現れた。日本人が生態系全体の中で積極的に自らの役割に貢献し、その生態系の一員であることを誇りに思っている様子は、時が経つにつれ明らかになっていった。

「御神木祭」の木引き行列。 共存とつながり。 敬意とコミュニティ。 充実感と目的。 笑顔と愛。 千年の時を経て作られた一枚の写真
森林浴や「Japan Shinrin-yoku tour 2024」ツアーの体験には、消費ではなく尊敬、個人主義ではなく共同体、利益ではなく持続可能性といった教訓が含まれている。もし誰もが、森林や自然に対する思いやりや敬意といった考え方を採り入れることができれば、環境問題の多くが直接的にも間接的にも解決に向かうのではないだろうか。
自然への敬意を忘れないことで、大規模な森林伐採、非倫理的な農業慣行、資源の乱獲、放棄、自然に反する政策を回避することができる。また地域社会への共感を持つことで、人為的な原因による山火事、森林の分断化、汚染、生物多様性の喪失、食糧安全保障の喪失を防ぐことができる。
そして、森林浴は、私たちをそこに導く第一歩となり得る。森林浴は、私たちの心身の健康を向上させるだけでなく、森林や地域文化への感謝の気持ちを学ぶための身近な方法を提供する。私たちの経験を個人的な投資に変え、かつて私たちの祖先がそうしたように、森との共鳴を求めるよう私たちを駆り立てるのだ。それを小野なぎささんの言葉を借りて表現すれば「人間が森のリズムで生きることができれば、自然との共存を続けていくことができる」と言えるだろう。
※本記事は、ハーチ株式会社が運営する「Zenbird」からの転載記事となります。
【参照サイト】一般社団法人 森と未来ホームページ
【参照サイト】 一般社団法人森と未来 プレスリリース| 世界最大の森林浴ネットワークと提携し「Japan Shinrin-yoku Tour 2024」を実施
【関連記事】山形県小国町で森を浴びる体験。白い森とマタギが教えてくれた自然観とは
最新記事 by Livhub 編集部 (全て見る)
- 【11/22-23開催】いのちをいただき、生き方を編み直す。「食の未来」を対話する旅 - 2025年11月5日
- 「夏のサントリーニ島はおすすめしません」仏・旅行会社が人気観光地を“ディスる”広告を出したワケ - 2025年7月3日
- オーバーツーリズムを超えて「人口過多」のバリ島。観光は悪なのか - 2025年6月25日
- 「原風景を守る」ための地域需要を。バリ島のハイパーローカルなレストラン - 2025年6月25日
- アジアの旅を、未来へつなぐ学びの場。GSTCとAgodaによるサステナブルツーリズム・アカデミーが開校 - 2025年6月25日