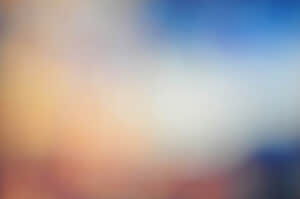前編では、高知の伝統工芸品である「刃物」と「和紙」に携わる4つの事業者の概要と実際に見学・体験したこと、印象に残ったことなどをお伝えした。後編では「酒」と「農業」に関わる4つの事業者について同様にお伝えし、最後には今回のオープンファクトリーツアーを主催する四国経済産業局がテーマとしている「地域一体型」の取組にしていくための視点やアクションを考えていく。
奥四万十の米と水で生まれた個性あふれる酒造店
原料の生産から造り手の働く環境までこだわる無手無冠
はじめに、四万十川の山間で明治26年に創業し、地元の米と水で仕込み、地元の匂いが香る酒造りを目指している無手無冠。有機肥料で育てた契約栽培米を使い、栗焼酎の搾りかすをその有機肥料に有効活用するなど、循環型醸造法が特徴で、自然と共に育むこだわりの酒造りを行っている。訪問当日は喜田杜氏に酒蔵を案内いただいた。
無手無冠の看板商品であり、高知を代表する「ダバダ火振」は、四万十の特産品の一つである栗を使った焼酎。きっかけは栽培が全盛期だった1980年代に、当時の町長から規格外や獣害などで廃棄となってしまう栗を使えないかと相談をもらったことだった。それまで製造していた日本酒とは異なる製造方法のため、新たに酒造免許を取得するなど苦労の末で栗焼酎が完成。その後、JALの国際線にて機内販売として採用され、国内外で人気商品となった。見学を通して、地域に根付いた酒造りに大切なことを、ダバダ火振を生み出した先代の杜氏を引き継いだ喜田和亨氏に尋ねた。
喜田氏は「日本は人口減少社会で、焼酎離れも進んでいる状況。ビジネス的には国内だけでなく、海外への展開も必要となる。ダバダ火振も四万十産の栗の他に、イタリアの栗を使った商品も生産している。そして、それらを安定的に生産するためには、酒の原料や酒がきちんと発酵できる環境がポイント。私たちは地元農家と協力し、農薬を使わない米作りを行い、その際に栗焼酎の製造過程で出る搾りかすを有機肥料として活用している。また、酒造りは体への負担も大きい仕事のため、機械化や自動化も導入しながら、蔵人の働く環境を整えることも重要」とおっしゃった。
出来上がった商品の美味しさだけでなく、原料の生産から造り手の環境までこだわることによって、地元に愛され、世界にも愛されるブランドに育っていくのだと感じた。
町に唯一残った酒蔵で、新たな価値を生み出す文本酒造
続いて、四万十町本町にて地域ブランド米「仁井田米」と「四万十川の水」を使った日本酒などの製造・販売を展開する文本酒造。1903年に創業し、2020年に酒造りを休止。その後、第三者事業承継を行い、2023年に「fumimoto brewery」として生まれ変わる。地域特性を最大限に活かし、地域とともに繁栄する酒造りを行っている。訪問当日は現杜氏の石川博之氏に酒蔵を案内いただいた。
文本酒造がある旧窪川町にはかつて8つの酒蔵があった。しかし、人口減少や過疎化が進み、気づけば、醸造を続けているのは一番古くからある文本酒造のみとなっていた。その文本酒造もコロナの影響で廃業の危機を迎えた。そんな危機的状況を憂えた町の有志の声に応える形で、現経営陣が事業を承継し経営を立て直すことに。酒造りの最高責任者にあたる杜氏には、茨城県笠間市の酒蔵で25年以上酒造りをしていた石川氏を招聘し、「fumimoto brewery」としてリスタート。見学を通して、なぜ縁もゆかりもない四万十の酒蔵にやってきたのか、生まれ変わった文本酒造をどうしていきたいかを石川杜氏に尋ねた。
石川氏は「茨城県の酒蔵で杜氏を約14年勤め、退職したタイミングで全国の酒蔵から声をかけていただいた中に文本酒造もあった。ここは単なる継承というよりは再生。50歳を過ぎ、新しいことに挑戦できる機会はなかなかないと思った。ただ、実際に現地を訪れたら、休業していたこともあり、蔵の状態が悪く、一度はお断りをした。それでも事業を引き継いだメンバーが醸造再開に向けて必死に整備をしている状況を見て、オファーを受けることに。リスタートしてまだ1年半ではあるが、四万十が誇る仁井田米を使った酒造りと四万十の地域特性をフルに生かした取組が少しずつ形になってきた」とおっしゃった。
単なる酒を造る施設でなく、体験、買い物、飲食など、人が集まる、交流する拠点に生まれ変わったことによって、地域に新たな人の流れが生まれ、地域が活性化していくのだと感じた。
日本一の生産量を誇るニラ集出荷場と高知県初の滞在型市民農園
生産者と作業員の両方の働く環境をより良くしている高知県農業協同組合(四万十野菜集出荷場)
続いて、四万十町高西地区にて生産量・出荷量ともに全国1位で高知県が誇るニラの集出荷を行う高知県農業協同組合(四万十野菜集出荷場)。この施設は農林水産省の「令和4年度強い農業づくり総合支援交付金」を活用して建設。2023年8月からニラ専門の集出荷施設として稼働を開始し、同年は2000トンを出荷した。訪問当日は明神場長と島岡販売課長に施設を案内いただいた。
ニラの生産量・出荷量日本一とはいえ、近年は生産者や作業員の減少と高齢化、施設自体の老朽化などが課題となっていた。そこで最新の機械やシステムを導入した集出荷場を新設。ニラを収穫した後に外葉を取り除く「そぐり」、1束約100g程度にする「計量」、その後の「結束」「包装」と、工程ごとに生産者の作業をサポートできるように。その結果、生産者はニラの生産に集中し、出荷量を増やすことにつながっている。見学を通して、生産者以外の集出荷場の作業員や地域全体への影響について、明神氏と島岡氏に尋ねた。
明神氏は「作業員については、これまでに60名以上の雇用を創出してきた。地元の四万十町民をはじめ、須崎市や四万十市など隣市の方、特定技能外国人、障害者の雇用を行ってきた。また、ニラの生産が減る夏時期は、別の集荷場でミョウガやピーマンの作業を行うなど、年間通して雇用を安定化させている」とおっしゃった。島岡氏は「地域については、作業過程で出る残菜を堆肥センターにて循環させる取組を行っており、今年からは小学校などの社会科見学を受け入れ、食育活動にも力を入れていく予定」とおっしゃった。
最新のテクノロジーを活用することによって、生産者や作業員の両方の働く環境を整え、生産性を上げることができ、さらに環境に配慮した取組や地域に開かれた活動によって、未来の農業やその担い手となる子どもたちにプラスの影響を与えることができると感じた。
一人ひとりの住む動機に寄り添うクラインガルテン四万十
続いて、四万十町本堂にて高知県で初めてとなる都市と地域の交流を通じて、地域の活性化および移住・定住の推進を図る滞在型市民農園「クラインガルテン四万十」。この施設はクラインガルテン発祥地であるドイツへの視察等を経て、県立農業大学窪川分校の跡地を活用し、2010年に開園。それ以来、約15年間で25名が四万十町に移住、その内、約2/3が県外から来た人となっている。訪問当日は島岡管理人に施設を案内いただいた。
クラインガルテンとは「ドイツ発祥といわれている市民農園制度。元々は、農地の賃借制度として約200年前に始まったものが、様々な社会情勢を背景に市民農園運動に転じた。はじめは食料自給が目的であったが、社会の成熟とともに精神的安らぎを得る空間としてや、都市近郊などの緑地保全、あるいは環境教育のフィールドとして活用されている。日本でも90年代に入り各地でクラインガルテンが設置されている」(引用:クラインガルテン四万十のパンフレットにより)。年間約30万円〜44万円(区画によって異なる)の利用料で、1年毎の更新で最大3年まで住むことができる。見学を通して、島岡氏にクラインガルテン四万十に住んでいる人の特徴とどのように利用者の受け入れをしているのかを、居住者の方に移住してきた理由と住んでみての感想をそれぞれ尋ねた。
島岡氏は「ここに住んでいる人は、高知に完全移住を目指してやってきた方や農業をやりたい方、定年退職をしてセカンドライフをしたい方など、いろんな年代の人たちが住んでいる。それぞれの動機に寄り添いながら、週末にはイベントを開催し、住民同士で交流できる機会を設けている」とおっしゃった。神奈川からIターンで来た男性は「大学で農業の勉強をしてきて、就職も農業に携わりたいと思い、高知の会社への就職が決まった。その後、住む場所を探している時に、会社の先輩と管理人が知り合いでここを紹介してもらった。ここに住んでいる人たちとの交流はもちろんのこと、地元の消防団にも入ったことで、外からやって来た自分でも地域に馴染むことができた」とおっしゃった。
一人ひとりの住む動機に寄り添ってくれる管理人がいて、ほどよい距離感のコミュニティがあることによって、自分らしい暮らし方の実現を叶えることができると感じた。
おわりに 〜オープンファクトリーを地域一体型の取り組みにしていくためには?〜
今回、メディアツアーとして黒鳥鍛造工場、穂岐山刃物、井上手漉き工房、鹿敷製紙、無手無冠、 文本酒造、高知県農業協同組合(四万十野菜集出荷場)、クラインガルテン四万十の8事業者を訪問したオープンファクトリー in 高知。各企業への訪問を通じて感じたことや印象に残ったことはそれぞれ触れた。ここでは最後に、オープンファクトリーツアーを主催する四国経済産業局がテーマとしている「地域一体型」の取組にしていくための視点やアクションについて、高知ツアーに実際に参加した筆者視点で地域づくりの担い手となる人たちにお伝えしたい。
1、対比・差異を意味する「コントラスト」
1つ目の視点としては、対比・差異を意味する「コントラスト」。今回、「刃物」「和紙」「酒」「農業」の4つの分野からそれぞれ2事業者ずつ訪問した中で、同じ分野とはいえ、ものづくりの方法や生まれる効果などに違いがあると思った。刃物と和紙では、黒鳥鍛造工場と和紙を製造する井上手漉き工房は手作業中心の一方で、穂岐山刃物と鹿敷製紙は機械と手作業のハイブリッドを採用。酒では、無手無冠の搾りは上から圧をかける機械の一方で、文本酒造の搾りは横から圧をかける機械を使用。農業では、ニラの集出荷場を運営する高知県農業協同組合(四万十野菜集出荷場)は地域の雇用を創出する一方で、農園付きで滞在ができるクラインガルテン四万十は移住者を創出。こうした各事業者のものづくりにおける違い、コントラストが見えるアクションは、ものづくりに対する知識や見方が広がり、ものづくりへの関心を高めることにつながるだろう。
2、文脈や背景を意味する「コンテクスト」
2つ目の視点としては、文脈や背景を意味する「コンテクスト」。今回、8事業者を訪問した中で、高知の恵まれた自然環境と地域が抱える社会課題の2つの側面からものづくりを捉えることができると思った。日本一の森林率である高知は古くから林業が発展し、その伐採に打刃物が、また、その山で育った楮や雁皮などの木と仁淀川や四万十川などの清流の水で土佐和紙が、さらに、その清流の水と河川流域で育った米や栗で日本酒や焼酎がつくられてきた。その自然環境とそこから育つ原料を大切にしたものづくりが展開されていた。その一方で、人口減少・少子高齢化に伴う人手不足や後継者不足、グローバル化に伴う価格競争などに対しては、知恵と工夫でその文化や伝統を継承していた。こうした各事業者のものづくりにおける背景、コンテクストが見えるアクションは、単に完成したものだけでなく、その地域の歴史、自然、食やその人の技術、言葉、アイデアといったプロセス自体に価値を見出すことにつながるのかもしれない。
3、方向性や構想を意味する「コンセプト」
3つ目の視点としては、方向性や構想を意味する「コンセプト」。今回、各事業者のものづくりに対する考えや想いに触れた中で、コンセプトが明確にあるものづくりは地域の活性化、特に地域の子どもたちに大きなインパクトを与えるのではないかと思った。黒鳥鍛造工場の「自由自在な創造性」、穂岐山刃物の「世界に誇れる技術」、井上手漉き工房の「新しく価値づくりへの挑戦」、鹿敷製紙の「本質を追求する心」、無手無冠の「人と環境が循環する仕組み」、 文本酒造の「人と地域のつながり」、高知県農業協同組合(四万十野菜集出荷場)の「選択と集中ができる体制」、クラインガルテン四万十の「一人ひとりに寄り添う姿勢」。こうした各事業者のものづくりにおける方向性、コンセプトが見えるアクションは、ものづくりが行く先は単にものを消費して終わるのではなく、そこに込められた想いが人から人へ、地域全体へと浸透していくのではないだろうか。
このコントラスト、コンテクスト、コンセプトの3つの視点とアクションを地域側が積極的に取り入れることによって、オープンファクトリーは企業単体型の工場見学という「点」で、製造過程の見物や話を聞くことが中心の「一方向」の取組ではなく、地域一体型のものづくり体験という「面」で、製造行程の体験や対話することが中心の「双方向」の取組になっていくであろう。
また、地域一体型のオープンファクトリーに参加した人は、地域の自然や文化に触れたり、地域の人と交流したり、地域ならではの体験をしたりすることで、新たな学びと地域との関係を獲得することができるであろう。今回のツアーを通して、その未来を想像することのできた充実の2日間だった。
【参照サイト】株式会社無手無冠
【参照サイト】文本酒造株式会社
【参照サイト】高知県農業協同組合
【参照サイト】クラインガルテン四万十
【参照サイト】四国産業経済局
【関連記事】ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(前編)〜
Tadaaki Madenokoji
最新記事 by Tadaaki Madenokoji (全て見る)
- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月11日
- ものづくりの現場から地域の未来を紡ぐ 〜オープンファクトリーメディアツアー in 高知 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月11日
- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(後編)〜 - 2025年3月10日
- 持続可能な地域づくりのヒントは「地域一体型」にある 〜オープンファクトリーメディアツアー in 愛媛 取材レポート(前編)〜 - 2025年3月10日
- 離島から企業の事業開発×地域の課題解決を実現する 〜あいちの離島ワーケーション モニターツアーレポート(後編)〜 - 2025年2月28日