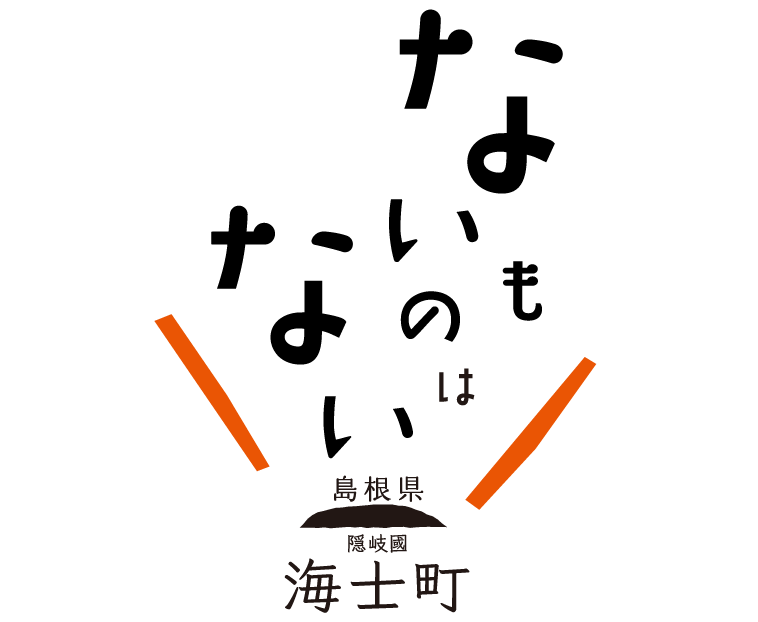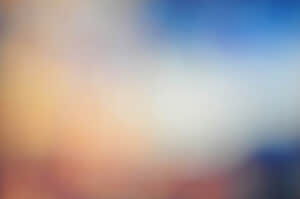Sponsored by 隠岐サーキュラーデザインラボ
以前自宅近くを散歩中、住宅地の片隅のプレハブで営業している野菜直売所を偶然見つけた。中に入ると、農家のおばあちゃんが1人で店番を担当していて、並んでいる野菜一つひとつの料理の仕方まで丁寧に説明してくれた。
「これは『かつお菜』って言ってね、お味噌汁に入れると美味しいのよ。それからこの『のらぼう菜』はね….」
大手スーパーでは経験することのない、おばあちゃんの「豆知識接客」は止まらない。なぜかその接客にはまった僕は、いつしか野菜の大半を直売所で買うようになった。そして直売所の農家の老夫婦が、丹念に育てた野菜を丁寧に並べる様子を目の当たりにするうちに、以前は捨てていた野菜を料理してみたり、切り落とした大根のヘタや葱の根っこを庭に植えて育て始めたり。おばあちゃんの豆知識のせいもあってか、いつの間にか自分の行動が少し変わっていることに気づいた。
・
「サーキュラーエコノミー(以下、CE)」「循環経済」という言葉をメディアを通して目にするようになった昨今。その言葉の定義や、必要性はわかってきた。けれど、次に「CEという概念を自分ごとにして、実践するためにはどう行動したらいい?」となると頭の中はぐるぐる…。そして気がつくとまたいつもの消費を中心とした生活に戻っている。そんなことを幾度となく繰り返してきた。
そんな状況を変えるには、自分が消費しているものがどこから来て、どこへ行くのか。その流れやものの循環を、体験や生産者との直接的なコミュニケーションを通して、体感することが大事なのでは?冒頭に書いた経験を通して、そんな疑問が浮かんだ。
その疑問の答えを探すために、2024年の夏にある旅へ参加することにした。その旅のきっかけをくれたのは、島根県・海士町(隠岐諸島)を拠点としてサーキュラーエコノミーをテーマにした活動を展開している「隠岐サーキュラーデザインラボ」の主宰者である藤代圭一さんと寺田雅美さんの2人だった。
インタビュー、そして海を渡り隠岐へ
今回の旅の縁は、2024年の春に行ったあるインタビューから始まった。Livhub及びサーキュラーエコノミーメディアプラットフォーム「Circular Economy Hub」を運営するハーチ株式会社が、東京都との協働により展開した「Circular Startup Tokyo」というCE領域に特化した創業支援プログラム。そちらにエントリーしていた「隠岐サーキュラーデザインラボ」のお二人に創業のきっかけを聞くインタビューを筆者が担当した。
 島根県海士町在住。隠岐サーキュラーデザインラボ主宰。問いを通じたアイデア創出やコミュニティづくりを得意とする。50年ぶりに刷新された海士町役場では島民と協働し、旧庁舎・ホテルの廃材を活かして家具の8割をリメイク・リユース。また、資源と物語がめぐる旅「GREEN ACADEMY」を企画し、全国の循環事例を学び合う視察プログラムを運営。著書『私を幸せにする質問』ほか。
島根県海士町在住。隠岐サーキュラーデザインラボ主宰。問いを通じたアイデア創出やコミュニティづくりを得意とする。50年ぶりに刷新された海士町役場では島民と協働し、旧庁舎・ホテルの廃材を活かして家具の8割をリメイク・リユース。また、資源と物語がめぐる旅「GREEN ACADEMY」を企画し、全国の循環事例を学び合う視察プログラムを運営。著書『私を幸せにする質問』ほか。
Instagramアカウント

海士町(隠岐)&東京の二拠点暮らし7年目。学生時代の科学記者との出会いを機に、「サイエンス×社会」の橋渡し役として科学コミュニケーションに従事。進化生物学者を志していた背景から、「自然×人」の橋渡し役としてインタープリテーション・環境教育にも携わる。「多様な人が集う対話、共創の場づくり」が未来をつくると信じている。現在は、隠岐ユネスコ世界ジオパークのガイドとして「大地の成り立ち」「独自の生態系」「人の営み」に魅せられており、海外ゲストとのジオ書道・野点にはまる。また、近年は「文化観光」による地域への再投資の仕組みづくりに、教育×観光の沢山の皆さんと奔走中。国内外をめぐるフィールドワークアカデミー「GREEN ACADEMY」をぜひ他地域を巡りながら展開したいと考えている。
そして掲載したインタビュー記事がこちら。
仲間の輪から生まれた”循環”を事業に。隠岐発スタートアップ「隠岐サーキュラーデザインラボ」が描く未来
その取材の最後に、2人が企画する「資源循環」を学びあうフィールドワーク「GREEN ACADEMY」開催の知らせを聞き、「これは参加せねば!」と直感したのだった。

“GREEN ACADEMYとは、1年間を通じて、複数の地域をめぐりながら、多様な地域に根ざした、循環モデルの事例(具体事例と挑戦事例・課題)を学びます。また、実践者や地域とつながり、現地での対話を通じて、語り合い、お互いに新たなアイデア・CE事業を創造・共創する場をつくります。”
そんな経緯で、このコンセプトに共感した筆者を含む参加者6名は、2024年7月に僕たちは島根県の離島、隠岐島へ2泊3日の旅へ向かった。
隠岐諸島ってどこにある?
今回の旅の舞台となる隠岐諸島は、島根・鳥取の県境から北方約60kmに位置し、約180の島と4つの有人島がある。海洋生物や漁業などの人の営みも含め、隠岐を取り巻く環境そのものが、「隠岐ユネスコ世界ジオパーク」として認定されている。
アクセスに少し手間はかかるが、それだけに価値のある豊かな自然の宝庫となっているのが隠岐諸島だといえる。ちなみに詳細の交通アクセス情報についてはこちらの一般社団法人隠岐ジオパーク推進機構のサイトを参照のこと。
そして海士町を象徴する言葉であり、島らしい生き方や魅力、個性を堂々と表現するキャッチフレーズとして有名なのが「ないものはない」という言葉だ。
この言葉は海士町のロゴマークにもなっている。このフレーズに込められた意図が、今回の旅のテーマにもつながっていると感じたので、梅原真氏のコメントを以下に引用する。
僕もローカル(高知県)に住んでます。
条件がいいところではない。
しかし「良し」も「悪し」もその土地の個性だと思うのです。
その個性の上に、生きていく生き方を考える。
それが「ユタカ」なことです。
もっとほしい、もっとほしい、もっとほしいと言っている人間が、なんだか変なことにしているような気がしてる。
「ないもの」は、なくていいんじゃないの?
「大事なもの」が、ここに全部あるんじゃないか?
「ないものはない」
離島・海士町の本質を語るとこの言葉になりました。
これは海士町の本質でありながら、地球全体の本質ではないのか。
そういう思いを僕はもっています。
そして隠岐島に関心のあるフィールドワーク応募者5名に加え、まさにこのテーマにぴったりなゲスト、ゼロ・ウェイスト・ジャパンの坂野晶さんを迎え、参加者一行は七類港を出発。フェリーと高速船を乗り継ぎ、島根県海士町の菱浦港(ひしうらこう)に降り立った。

ちなみに坂野さんはこんな方。
 兵庫県西宮市生まれ、鳥好き。絶滅危惧種の世界最大のオウム「カカポ」をきっかけに環境問題に関心を持つ。大学で環境政策を専攻後、モンゴルのNGO、フィリピンの物流企業を経て、日本初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った徳島県上勝町の廃棄物政策を担うNPO法人ゼロ・ウェイストアカデミーに参画。理事長として地域の廃棄物削減の取組推進と国内外におけるゼロ・ウェイスト普及に貢献する。米マイクロソフトCEOらとともに、2019年世界経済フォーラム年次総会(通称ダボス会議)共同議長を務める。2020年より一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパンにて循環型社会のモデル形成・展開に取り組む。
兵庫県西宮市生まれ、鳥好き。絶滅危惧種の世界最大のオウム「カカポ」をきっかけに環境問題に関心を持つ。大学で環境政策を専攻後、モンゴルのNGO、フィリピンの物流企業を経て、日本初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った徳島県上勝町の廃棄物政策を担うNPO法人ゼロ・ウェイストアカデミーに参画。理事長として地域の廃棄物削減の取組推進と国内外におけるゼロ・ウェイスト普及に貢献する。米マイクロソフトCEOらとともに、2019年世界経済フォーラム年次総会(通称ダボス会議)共同議長を務める。2020年より一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパンにて循環型社会のモデル形成・展開に取り組む。
あまマーレを起点につながるローカルと移住者
対馬暖流のおかげで年間を通して温暖な海士町。訪れたのは7月後半、半袖でも歩いているうちにじんわり汗が浮かぶ夏らしい日差し。
フェリーが行き交う海、まだ濃い緑に覆われた田んぼ、見慣れない赤い瓦の建物。港から車で移動するぼくたちの横を、隠岐の見慣れぬ風景がスライドショーのように飛び去っていく。フィールドワークへの期待と慣れない場所での不安が入り混じり、初めて異国の地に降り立ったような気分でそわそわきょろきょろ。
そして辿り着いたのは、森に囲まれた、白と茶色の味のある平屋の前。今回の旅の始まりは、中ノ島・海士町の元保育園の建物を活用したコミュニティ施設「あまマーレ」からスタートした。
あまマーレは、町民の「海士町で暮らす楽しみがひろがっていくこと」を目的に、さまざまな活動が行われる施設だ。子供部屋や遊戯室に加えて、自由に使える貸切スペースなどがあり、もちろんWi-Fiも完備。年間を通してさまざまなイベントが行われている。
館内を散策しているうち、参加者の一人が気になる古道具やさんを発見。店内には昭和レトロな食器や台所用品、家具や着物など、さまざまな日用品が並んでいる。

「島内には大型店舗がないため、移住者には家具や雑貨などが手に入りにくいという課題があります。一方で海士町の最終処分場はあと数年で一杯になってしまうという課題もあり、島の住民は要らないものを捨てる場所に困っています。その『いる』と『いらない』をつなぐ場所としてこの古道具やさんが運営されています」
島民から不用品を引き取り、綺麗にしてから商品にしているという。また、あまマーレで生まれている循環はものだけではない。その一例としてスタッフの浜中さんは、ここで行われているイベント「島ばっば交流会」に関してこんな話を紹介してくれた。
「隠岐に移住者が増えたことで、元々住んでいる島民の皆さんから『あの奥さんはどこの人?』という会話を聞くようになりました。それをきっかけに、人生の先輩としていろんな能力を持つ島のお母さんたち=『島ばっば』と、移住者の子育て中のママの交流の場をつくろう、という目的で交流会がスタートしました。茶話会から始まり、2回目以降はこんにゃくや煮しめなどの島の郷土料理を皆で一緒につくるなど、交流が深まりながら、自然に伝統料理の継承にもつながっています。そういった交流を企画してくれたのが、島の集落支援員として活動していた扇谷さんでした」

<島ばっば交流会の画像>奥から2番目が発案者の扇谷さん( あまマーレ公式サイトより引用)
この島ばっば交流会がきっかけとなり、島の中に頼れる両親や知人がいない移住者の子育て世代も、仲良くなった島ばっばに少しの間だけ子供を預けるような関係性ができたそうだ。
このかつて保育園だったあまマーレでの交流会や古道具やさんを起点に、島民や移住者という枠を越えて、ものと想いの循環の輪がひろがり始めている。かつての島の保育園は、いまやより多様なものを育む場に移り変わっているようだ。
おからドーナツとともに巡る島の記憶
太陽の光を反射しながら鈍色に光る瓦屋根。建物が歩んできた歴史を物語る土壁と木の柱が印象的な古民家の前に到着した参加者たち。正面には「アヅマ堂」という看板があり、その横には猫が欠伸をしながら居眠りをしていそうな、細い路地が店の入り口へと続いている。
ここは築90年以上の古民家を受け継ぎ、島の人気のお菓子屋さんとなった「アヅマ堂」。昔ながらのつくりの温もりのある店内には、オリジナルのドーナツやお菓子が並んでいる。

おからドーナツ「亀ド」 海士町公式noteより引用
特に丸い形が特徴のおからドーナツ「亀ド」は、すぐ近くの豆腐屋兼商店「亀田商店」の副産物であるおからと豆乳を材料につくられている看板商品。このドーナツは地元住民にとても愛されていて、その美味しさと1個30円という手頃な価格のせいもあり、下は1歳から上は99歳までファンがいるほど。
そして店内にはお菓子に混じって、美しい花や鳥などが彫られた木型が並べられている。これは一体なんだろう?お店の成り立ちも含め、店主の大野祥子さんに聞いてみた。

オーナー夫婦の大野祥子さん、大野圭佑さん image via「自立」と「共存」の島暮らし──大野佳祐さん・大野祥子さんに聞く、海士町で暮らし、つくる6年間
「ここは築90年ほどの建物で、元々は『阿津海堂(あづまどう)』という和菓子店でした。2014年に島に移住後、海士町らしいグラノーラを販売するプロジェクトに夫婦で取り組みながら製造場所を探していたところでこの空き家に出会い、運命を感じました。
その後この物件を購入し、再び菓子店として営業を開始しました。店内には当時の和菓子の木型や箱なども残っていたので、それらを大切に使っています。建物に関しても建物の元の持ち主への敬意を大切にしながら、当時の雰囲気を壊さないよう心がけています。80歳以上の地域の方々からは、当時の和菓子店での思い出話を聞かせていただくこともあり、そんな地域の繋がりを大切にしています」
人口も少なく、高齢化も進んでいるこの隠岐諸島中ノ島において、素材の調達はどうしているのだろうか。
「島では生産者が高齢化しているので、原材料の生産が限られています。アヅマ堂オリジナルのグラノーラ『あまノーラ』の材料の黒豆を仕入れる時も、島民のおせち料理の分がなくならないように配慮しながら発注します。島では買う側の方が生産者よりも強いわけではありません。生産者をやめてしまう方も多い中、『これだけの材料が必要なので分けてください』とお願いする形です。
ただ島内の材料100%にはこだわっていません。良いものは島外からも仕入れ、バランスを取りながら商品開発をしています。島のいいところと他のものを組み合わせることで、より良い商品を作ることを心がけています。そもそも私たち夫婦も島産ではないですしね」と語る大野さん
豆腐の副産物であるおからで作られた丸いドーナツが、島民の食卓を巡る。受け継がれた古民家とかつての和菓子道具をきっかけに、懐かしい思い出が島民の間を巡る。そんな場所であるアヅマ堂には「ないものはない」というキャッチコピーを掲げる海士町らしい循環を感じる。
「もしかしたら海士町の循環は『もの』以外のところにあるのだろうか?」そんな想いを抱えながら、店の外に出て町を眺めると、それまで馴染みのなかった風景が、なぜか少しだけ身近なものに感じてくる。そして「今日のおやつはドーナツだな」と心に決めて店を後にした。
後日談として、この来訪時の店主大野さんは、海士町でのチャレンジを糧に、現在はセブ島での出店準備中だとか。現在は、大野さんから想いを引き継いだ島の友人が新たな店主となり「薬膳カフェ 東風Kochi」をシェアキッチン事業とあわせて切り盛りしている。大切にされてきた「阿津海堂(あづまどう)」では、今日もたくさんの人の日常・旅のしあわせな1コマが紡がれている。
種の図書館「シードライブラリー」が未来に巡らせる、島の固定種
フィールドワークの中で、海士町には「本以外のものも町に巡らせる図書館があるらしい」という噂を聞きつけ参加者たちは「海士町中央図書館」へ。そこには本だけでなく、植物の種が貸し出されていた。

この「シードライブラリー」という取り組みは、本の貸し借りと同じように野菜や花の種を貸し出すというもの。図書館から種を借りて育て、うまく収穫できたら種を返す仕組みだ。農業に取り組む住民グループ「暮らしに楽しみの種をまき隊」と2020年3月から共同運営しており、タネの情報交換会などのイベントも実施している。
そのグループの代表をしているのが、宮﨑 雅也さんだ。
「最初は固定種の種の交換会イベントから始まりました。海士で長く育てた野菜の種は、海士の気候や風土を記憶して育ちやすくなります。そしてその種の交換の仕組みが常に町のどこかにあれば、自分の畑で種がとれなかったとしても島の皆でシェアし合うことでリスクヘッジになる。そんな理由からシードライブラリーがスタートしました」
これまでシードライブラリーという取り組みは沖縄にもあったそうだが、実際の図書館で種をシェアする試みは初めてだとか。そして宮崎さんがこの取り組みを続ける動機の根本についても聞いてみた。
「商業的な野菜栽培のために交配して作られた『F1』と呼ばれる種が主流になる中で、島で守られてきた伝統的な在来種を保存して後世に引き継ぐことも大切なことだと感じています。地域に合った美味しい野菜の種、というのは、この世で最も価値があるもののひとつだと思っているので、今後も、種取り仲間を増やしながら、続けていきたいと思っています」
それまでやわらかくふわっとしていた彼の語り口とは対照的に、その最後の言葉は力強かった。
「あなが次の世代に引き継ぎたいことは?」この時、宮崎さんからそんな問いを投げかけられた気がした。
後編に続く
【参照サイト】note | 隠岐サーキュラーデザインラボ
【参照サイト】ないものはない|Naimono wa nai|海士町公式ウェブサイト
【参照サイト】GREEN ACADEMY モニターツアー募集サイト
【参照サイト】ないものはない 海士町公式 note
【参照サイト】あまマーレ – 海士町のあそび場
【参照サイト】アヅマ堂
【関連記事】「いってらっしゃい」と「おかえり」を繰り返す、隠岐の循環をたどる旅路。Green Academyツアーレポート後編
Photo and text by Kazuto Ishizuka
いしづか かずと
最新記事 by いしづか かずと (全て見る)
- 「いってらっしゃい」と「おかえり」を繰り返す、隠岐の循環をたどる旅路。Green Academyツアーレポート後編 - 2025年9月18日
- 「いってらっしゃい」と「おかえり」を繰り返す、隠岐の循環をたどる旅路。Green Academyツアーレポート前編 - 2025年9月18日
- 茅ヶ崎でコーヒーと本を片手に”まちの日常”にふれる。分散型まち歩きコーヒーフェス「Takasuna Greenery Coffee Festival vol.4」初の2日開催! - 2025年4月30日
- 領域を越境するクラブツーリズム株式会社。コミュニティづくりで切り拓く新規事業の可能性 - 2025年3月4日
- 奥会津のローカル線沿線で、自然と共生する暮らしを体感。暮らすように旅する「奥会津ワーケーション」の魅力 - 2025年2月24日